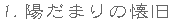
-1-
青空は、嫌い。自身の遅い歩みを、頭上遥か高くに広がる蒼穹の所為だと、舞阪華保は決め付けた。憎らしげに呟いたのは、これで何度目だろう。
照りつける日差しはチリチリと肌を焦がしている。真夏にアスファルトの道路を歩き続けるのは、それだけでも充分体力を消耗した。
勿論、遅々として進まないのは自分の脚が巧く機能してくれない所為であり、空の所為でないことは判っている。何かの所為にしてしまいたい、弱い心の所為であることも。
変わらなければ。そう思ったからこそ、今日がある。
この先にあるリハビリテーションの施設で、新たに見つけた目標をこの手にするのだと決意した。こんな出だしで挫けてるわけにはいかない。
何度も何度も己の気持ちを叱咤しているのだけれど、いかんせん身体が鉛を沁み込ませたように重い。
帽子、持って来るべきだったな。
まさに後悔先に立たず。言葉が脳裏に浮かんだ直後、嘲笑が短く漏れた。
この脚がこうなることを、後悔することを知っていたら、あの時の自分は、回避しようとしていただろうか。
あれは、兆候に目をつぶり、誤魔化し続けたツケを払ったに過ぎない。総ては己の責任でしかない。
頭では充分すぎるほどに理解していても、時が経つにつれ募る一方の悔恨の念。
戻れるのなら、時間を捲き戻せるのなら、自分は一体どの時点に還りたいのだろう?
後悔は人を曇らせる。――あれは誰の言葉だったろうか?
どうせ曇ってしまうのなら、いっそのこと世界中が曇ってしまえばいい。それらに全部覆われて、青空なんて消滅してしまえばいい。
益体無いことに思考を巡らせるより、今やるべきことはこの事態の改善を図ることだ。と、意識を現実に戻す。
気持ちを切り替えようとした矢先、膝からストンと力が抜けた。
歩く人間が少ないからといって申し訳程度にしか造られなかった歩道に、ペタリと座り込む。陽の熱を充分に吸収したアスファルトは熱く、かといって反射的に動けるほどには肢体に力が入らない。身体が重い。
空が、圧し掛かってくる気分だった。風にさざめき枝葉を揺らす音は、まるで華保を嘲笑しているみたいで。
膝はじくじくとした鈍痛を訴えている。サポーターの上に置いていた手を、ぎゅっと握った。
「役立たず」
誰にともなく呟く。
ぐるぐる頭の中を巡る一つの情景が、気分を更に最悪な方向へと導いていく。
アスファルトから身体に熱が染み込んで、ヒリヒリと悲鳴をあげつつあった。
火傷するかも…。
どこか暢気にそんなことを思っていたら、唐突な引力が華保を引っ張り立たせた。
「なに座り込んでんだよ。干上がんぞ?」


