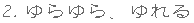
-2-
現場には、数名で形成された小さな塊があった。その外周で、避けるように、けれど好奇に満ちた表情で当事者達を遠巻きに見ている者の姿がいくつもある。その人垣をすり抜け、中心へと進む。小さな塊は他校の制服を着た男子生徒だった。塊の中に同校の制服を見つけ、その顔が確認でき、駆け寄った。身を竦め、声を投げられる度怯えを増していたのは、詩姫だった。クラスメイトと身を寄せ合い、今にも泣きそうに見える。
「詩姫っ?」
声に反応してからの詩姫の行動は早かった。クラスメイトの手を引き素早く塊から抜け出し、智姫の腕に抱きつく。背に隠れる格好でぴったりと寄り添った。
振り返り、智姫と詩姫を見比べる他校生は、お世辞にも素行がよさげな外貌とは言い難い。威烈な視線は対峙する者を威嚇していた。
「詩姫、大丈夫?」
声を出せないのか、こくりと頷く。
「知り合い、じゃないよね?」
激しく数度頷く。たまたま掴まってしまったということなのだろう。
「へぇ、双子か」
興を見つけた笑みは、不快そのもので。ゆっくりと近づいてくる顔を、睨み据える。
「そっちに訊いてたんだけど、別にあんたでもいいや。生徒会長を連れてきてくんないか?」
す、と背筋を伸ばし、詩姫を背後に庇う。
「それなりの手順踏んだらどう?こんなところまでズカズカ入り込んできて、人にものを尋ねる態度じゃないよね」
周囲の野次馬にどよめきが走る。智姫は怖面相手に少しも怯んだ姿勢はとらずにいた。理由は二つ。妹を怯えさせた相手に怒り心頭だったし、妹に害を及ばせるわけにいかないなら、虚勢だろうが何だろうが、凛とした態で挑むべきだと判断した。
相手の笑みに、面白い、と浮んだのが判った。その後ろに控えている他校生数名には、野次馬同様の苦いものが浮んでいる。一歩手前に出ているのがリーダー格なのだろう。仲間内でも彼にこんな口調をぶつけられるものではなく、智姫のような平均的な容姿の者に、強気な態度を向けられるのは珍しいことなのかもしれない。
「用件は?」
低く吐き出す。あくまで冷静に対応しているのだと、全面に押し出した。
せり上げる不快感を懸命に喉の奥に停滞させ、睨めっこが如く双眸を見上げ続けた。
「そいつに話すよ」
「だから、あたしは面識がないと思ってるんだけど。どこかで会ってる?」
「は?」
「あたしが生徒会長なの。用件は?」
端的に切り返す中で、相手の顔をじっと観察し、脳内では記憶の引き出しを片っ端から開けていた。人の顔と名前を覚えるのは不得手ではなかった筈なのだけれど、どこからも一致情報が探り出せない。
「最上雅司ってのが生徒会長じゃねぇのか?」
ぴんとくる、を体感。雅司に、というのであれば、考えられる訪問内容はおおよそ検討がついた。
下らないな、と醒めた心地になる。男の見栄なのだろうか。
「二名就任制だから」
「俺が用事あんのは男の方だ」
「いくら粘ったって呼ばない。早く出て行った方が身のためだと思うけど?」
智姫の強気発言を受けたかのようなタイミングで教師の姿が見え、男達は見事なまでの逃げ足で去っていった。



