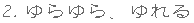
-5-
放置していたわけではない。誰にともなく言い訳がましいことを声に出さずに弁明する。誰かに向けてではなく、しいて言うなら、自分自身に。
慌しく廊下を駆ける。呼びにきた二人組は、雅司を先導して数歩前を走っていた。その背中を見失わないように注意を払いながら人の合間をすり抜ける。
――どうしたものか。
授業終了のチャイムのあとも思案継続だったが、何一つ良策は浮ばなかった。
消しゴムの一件は詩姫だったと言い張る。つまり、入学したての頃からずっと、智姫はこうなることを見越していたことになる。詩姫の想いがどこに向いてもいいように、予防線を張っていたことになる。おそらく当時に、予感させる何かがあったのだろう。
予感が確信に変わる何かが最近発生し、秀司から離れる手段として選んだのが「嫌われる」という方法。安直だが、効果的な。
だから、動かなかった。己の想いを封印し続けた。不器用極まりない智姫の想い。
(あぁ、もう、面倒くせーな)
面白半分に刺激したことを今更ながらに後悔する。奥底に隠していた智姫の我慢にまで覚っていたら、違う今があった筈だ。雅司に非がないとは言い切れない。
(余計なお節介なんて慣れないことをした代償だな)
走りながら苦く笑う。思考に囚われ若干速度の落ちた雅司を振り返り、前方を行く友人達が急かす。
「雅司!急げって!」
「わーってるよっ」
雅司の教室に飛び込んできたまんまの形相に、苦笑を洩らすしかなかった。
――双子が喧嘩してる!
第一声は休み時間の喧騒を切り裂いた。
さてどうしたものか、と考えあぐねていた矢先。直線的に雅司目掛けてくる友人二人を、ぽかんと迎え入れた。
「俺ら、喧嘩なんてしてねーぞ?」
我ながら惚けた声だな、と笑えた。北條姉妹のように仲良くはないが、目を合わせれば角突き合いするほど悪くもない。殴り合いでもしている現場ならばいざ知らず、視界のどこにも片割れがいない状態で「喧嘩してる」などと慌てられても反応のしようがない。
「お前らじゃなくて、姉妹の方。かなりキレてるってよ」
ああそっちか、と同時に、何故自分を呼びにくるんだよ? が先に立った。続いて、北條姉妹が喧嘩をしているという、雅司の感覚からしてみれば荒唐無稽な事柄に、鼻で笑ってしまいそうになった。その荒唐無稽さは他の者にとっても同感覚なのだと至り、焦燥に駆られる姿は普通の反応なのだと納得がいった。
そしてやっぱり、何故自分が指名されるのかと疑問が浮かぶ。
「珍しいな、あいつらが喧嘩とか」
入学してすぐに北條姉妹とは仲良くなった。そこから思い返してみても彼女らが喧嘩しているのを見たことがない。
「のんびり言ってんなよ。早く行こうぜ!」
だからなんで俺なんだ、は飲み込んだ。
雅司の交友関係は広いといえる。広く浅い。その深度はどこをとっても同じだと認識していたが、傍目からであれば、雅司が自覚しているよりも差があるのかもしれないな、と感じずにはいられない。こうして雅司にストッパーを持ち掛けるのが、何よりの証拠だ。
「お前らで止めればよかったんじゃねーの? 現場にいたんだろ?」
さっきの言い廻しであれば現場にいなかったと判断できるものの、あえて暢気な態度をとった。そうしていなければざわつく厭な予感が大騒ぎしそうで。
「喧嘩になってるって聞いて雅司を呼びにきた」
「人間凶器の智姫が手ぇあげたら、詩姫が壊れちまうな」
冗談めかしてみたものの、想定外の出来事に戸惑っているのは雅司も同様だった。
野次馬の輪は散開しつつあった。まばらに散り始める人波を逆走する格好で騒動の中心を目指す。
そこに自分と同じ容姿を見つけ、速度を緩めた。自分が出るまでもなかったな、と走った体力を返せと内心で罵った矢先、詩姫の槍声が飛んだ。
「ちーちゃんなんて、大っきらいっ!!」
音量にも驚いたが、放たれた言詞にも驚いた。凍りつく周囲に反して、爆弾を投下した詩姫は走り去って行く。誰よりも凍りついていた智姫の瞳は潤んでいた。頬の片方に赤みがさしている。
雅司と秀司の両名の視線を浴びながら、智姫は去っていく妹を凝視したまま微動だにしない。
「なにがあった?」
智姫にならったわけではないだろうが一緒になって固まる秀司を差し置いて、当然出て然るべき疑問をぶつけても、智姫は詩姫の背中から目線を剥がさない。
「ち、」
「嫌いって言われた…。詩姫が、嫌いって…」
茫然自失で呟く智姫の胸中は計り知れない。同じような内容を更に繰り返し「どうしよう…」で締め括られた。途端、くしゃりと表情を崩すさまは、幼子よりも子供じみていた。智姫は、こと妹絡みとなると姉御肌が綺麗さっぱり消滅する。
「これって、あたしに生きるなってこと?」
とパニくられても、状況が欠片も掴めないとなれば変な慰めもできやしない。
「あー、はいはい。とりあえず手当しようぜ」
「手当て?」
言葉の意味すら理解できてないといった風に智姫は雅司を見上げ、困惑するばかりだった弟は雅司の提案に素早く同意した。
べそっかき面で見上げられると、どうにも自分が苛めた気分に陥る。双子が喧嘩するだの、智姫が弱りきってるだの、有り得ない事態の所為だ。
舌打ち気分を引っ込め、雅司は自身の頬を引っ掻く所作をとる。
あの詩姫が? と信じられない心地だったけれど、他に考えられないだろう。
雅司の真似をして自分の頬に指先が触れた瞬間、しかめる。平手打ちの土産に、引っ掻き傷まで残っていた。掠める程度とはいえ、智姫を更にへこませるには充分だった。
「なにがあった?」
沈んでいる時に追及すべきではないかもしれないが、こんな状態でもなければ智姫が口を割らない頑固者だと知っているだけにあえて問う。弟の鋭い視線は無視した。
「……言わない」
小さく消え入りそうな音量だが、強固な意志は揺ぎ無いようで。
隙がないのかよ、と少々辟易した。



