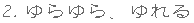
-6-
嫌いじゃない。ずるいだけ。彼のどこを嫌いになれというのか。自分からなれないのであれば、なってもらうしかない。
自分はきっと、自分を嫌っている相手を想い続けられるほど、強くないから。
協力を仰いだ者に、手放しで加担してもらえるなんて甘いことは期待してなかった。当然の反応だと、妙に醒めた心地で、彼と同じ造りの顔を眺めた。
――自分は、ずるい。
判っていて、けれど、他にどうしようもなかった。
怖かった。産まれる前から共に生きてきた妹に、嫌われたくなかった。
でも、結局、怒らせた。
怒られた原因は判っていたけれど、何故怒るのか理解できなかった。
ひどく、距離を感じた。
痛かったのは叩かれた頬ではなく、怒っている妹の泣き出しそうな顔が対峙した瞬間の、胸の軋み。
どこで、間違えた?
下した判断は、正しくなかったというの?
間近に人の息遣いを感じる。規則正しく綴られる寝息。
意識が夢の中からじんわりと現実へと浮上して、まどろむ心地よさに目蓋を開けず、自身の呼気と重なるように綴られる音を聞いていた。
安穏とした寝息が懐かしい。
本当に小さかった頃は詩姫と一緒のベッドで眠っていた。中学に入ってそれぞれの部屋が与えられた後も、互いのベッドに潜り込んでは眠ることが多かった。
段々と回数は減り、今では一緒に眠ることもなくなっていたけれど、誰かの眠りを身近に感じる安心感に、もう少しだけまどろんでいたかった。
これまでそうしてきたように、寝息の主の方へ手を伸ばした。髪に触れ、撫でる。詩姫の猫っ毛を撫でるのが好きだった。柔らかな髪とまどろむ優しい空気。互いに呼応し合う呼吸。
「詩姫…」
寝惚けながらも呼べば、妹は寝惚けた声で応えてくれた。髪を撫でれば、撫で返してくれた。けれど今は、その反応の総てが無い。
「…詩姫?」
指先に触れる感触が、覚醒の浮上と共に研ぎ澄まされていく。妹のそれとはまるで違う。――そう結論が出るや、スイッチを入れる切換えの速さで智姫は目蓋を開けた。
いつもは見上げる位置にあった顔が、自分と同じく、机上にある。ひどく近い。自身の手が彼の頭にあって、感触が違うのは当然だ、と思い、これが現実なのだと遅れて認識した途端、弾かれたように身体を起こした。
そのまま勢い余って、椅子から転がり落ちた。派手な物音がして、あまりの痛さに呻いている隙に、一緒になって居眠りしていた主――秀司が目覚めた。
上半身を起こし、何かを思い出すように目の前の宙を眺め、首をゆっくりと巡らせた。床に転がる智姫と目が合う。
「ちー!?」
スカートが捲れあがるだの、脚がおおっぴろげになるだの、無様な姿にまではなっていないものの、尻餅をついた格好のまま、痛みの所為で動けずにいた。
秀司が差し伸べてくれた手をとり立ち上がる。ここ数日で様々なことが智姫の心情を渦めかせていたけれど、痛感のおかげでかえって静かな応対が返せた。
痛みに気をとられなければ抱えている想いに、押し潰されそうになるところだった。
「びっくりした。なんでいんの?」
「ドアが少し開いてたから、誰かいんのかなって覗きにきたんだ」
昼休みだった、と思い出す。ぼうっとしているうちに眠気が降りてきて、机に突っ伏したところまでは思い出せた。その後のことは、ぷっつりと記憶が無い。室内時計に視線を転じ目を瞠った。
「うそっ。こんな時間!?」
「ぐっすり眠りこけてたもんなぁ」
どこか感慨深げに秀司は笑う。床に落ちていた制服の上着を拾って、それは智姫にかけられていた秀司のものだと知れる。
「起こしてくれたらよかったのに…」
苦々しく、声は尻すぼみになった。寝顔を見られ、かなり恥ずかしい。無防備な顔など、最近では家族にだって見せていない。
「起こしたけど駄目だった。あんまり気持ちよさそうに寝てるからつられたんだ。隙見せてると襲われるよ?」
冗談めかすなど、珍しい。自分がまだ寝惚けていて、兄弟を間違えているのかと気を引き締めてみるも、間違いなく秀司だった。
秀司が寝惚けているのだろうか。
「雅司みたいなこと言わないで…」げんなりと返す。「血は争えない、ってやつ?」
「心外だな。俺は相手をちゃんとみるよ。てか、ちーくらいにしか言わない」
やっぱり秀司は寝惚けているのだ、と結論付けた。
滅多に御目にかかれない秀司に、興を揺さぶられる。
「やっぱ、争えないね」
きょとん、と智姫を見る表情は幼く映った。
「雅司も相手見て言ってるらしいよ、あれでも。本気で受けちゃいそうな人には冗談でも言わないんだって。冗談で流すあたしとかには言える、って」
あくまで本人論なので、どこまで通用しているかは定かではない。少なくとも、智姫の目には分け隔てなく軽口を叩き続けているように映るのだけれど。
「あいつ…」
秀司は苦く言って、宙を睨んだ。
常が落ち着いた雰囲気を纏う秀司の意外な一面に、まずいことを言ったかなと湧いた疑点に気づかぬふりをする。悪いのは雅司の日頃の行いだ。
「ちー、頬平気?」
不意の真摯な声音に、居住まいを正された気分になる。ひゅ、と息を吸い込んで見遣った先にあるのは、いつもの柔和な秀司の顔。
「…うん。平気」
無意識に、頬へ指先が伸びた。傷に触れる直前で、手首を掴まれる。
「触ったら駄目だって」
小さな子供に諭すような穏やかな声。掴まれた手首と、真っ直ぐに射抜く双眸が見つめる自身の顔に、意識と熱が集中する。
大袈裟になるのは厭だからと、ガーゼも絆創膏もあてず、消毒と薄く薬を塗るだけにしてある。
「傷、残らなきゃいいけど」
憂えを帯びた瞳で覗き込まれれば、途端に鼓動が騒ぎ出した。
「だ、大丈夫だよ」
一刻も早く逃げ出したくなるのに、掴む手は緩まない。放して、と出る前に、秀司が智姫の名を唇に乗せた。
「喧嘩の理由は?」
「なんでもないよ」
「なんでもなくないだろ。普通じゃない」
なにがなんでも聞くまでは逃がさない、という気迫が感じられて、その気迫が詩姫とだぶり、泣きたくなる。
せり上がる感情を喉の奥で留め置いた。
「…言わない」
強い意志を表す為に、なにより、自身に決意の揺らぎを発生させない為に、端的に雅司に返した同じ言を放つ。
言えるわけなど、なかった。



