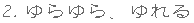
-7-
下校する生徒の影もだいぶ捌けた時刻を見計らって、ノックもなしに生徒会室のドアを開けた。予期した通りの状況に雅司は内心で笑む。闖入者の正体を確かめもせず、黙々と執務にあたる智姫の手には、常と変わらずダンベルが握られていた。室内には他に人の気配はない。
窓ガラス越しに見える空は群青色に染まりかけている。侵食されていく橙色が微かに認められるほどに残っているだけだった。
入口をくぐり歩み寄る足音と、整然単調に刻まれる秒針の音が、不調和に重なり合う。
「相手確かめるくらいの動きがあってもいいんじゃねーの?」
筆音は止まらない。上下するもう片方の手も止まらない。返事をする気も無いらしい。
「智姫?聞いてんのか?喩えばだ、侵入者が変態で、いきなり襲われたりすることも世の中には起こり得る事態なんだ」
「自身を変態と認めたってこと?」
不機嫌でも沈鬱でもない声だ、と安堵する。与り知らぬところで気負っていたのか、と気づき、苦笑した。自分に責がある、とは考えてもいなかったが、奥深いところでは引っ掛かりを覚えていたのかもしれない。
だからこうして、様子を見にきているのだ。と判断できなくもない。
「喩え話だっての。考え及ばぬことが起きることもあるって話。自分だけは大丈夫、なんて保証がないって説教」
ぴた、と手の動きが止まる。のっそりと上げられた顔にあるのは、胡乱げな双眸。同じ見上げる格好で、同じ造りの顔だというのに、双子を感じさせない対比差が人格の違いを浮き彫りにさせる。こういうところに愉楽を感じて、双子姉妹に関わりたがるのだろうかと自己分析してみる。
「説教とか、してほしくないんだけど」
「だな。俺もそう思う」
く、と口端を持ち上げ、智姫が座る執務机の端に腰掛ける。呆れたように息を吐き執務に戻ろうとする智姫からダンベルを取り上げた。男の腕力からすれば物足りなさを感じる程度の重量しかない。
「勇ましいよな。なんで鍛えてんの?」
「役割だから」
さらりと言う。軽々とダンベルを持つ雅司を斜に見上げた直後、視線をゆっくりと移動し、そこにはいない詩姫を見つめるように目を細めた。
「小さい頃から詩姫を護るのはあたしの役目だった。背中に隠れるあの子が安心していられる強さを手にしたい」
「畏れられることになっても?生徒会長こえーからなんとかしてくれ、って俺に言ってくる奴もいる」
殴り合いの喧嘩を止めに入った武勇伝あり、風紀を逸脱する輩に啖呵をきる勇猛な姿勢あり。同姓からは頼りにされるが異性からは遠ざけられる存在。
「こ煩い生徒会長なんて地位はさ、それくらいで丁度いいんだよ」
慣れてるし、と半ば面倒臭そうに言い足す。それから「中学の時に気になってる男の子に陰口叩かれたことあるし」と投げ遣りに付け足した。
「トラウマ?」
「まさか」
そんな単語が出るとは思わなかった、と顔に書いてある。これは外れらしい。正真正銘の正義感、ってやつだろうか。
「おねーちゃんだから?」
つまるところ、これしかない。智姫は条件反射よろしく頷いた。
「ずっと、そーゆうもんだって思ってきたし、実際、そーゆうもんなんだよ。上の子の宿命だよね、これって」
悲観も邪僻も感じられない。一種の洗脳みたいなもんなんだな、とぼんやり思う。
そこに、不憫さやいじらしさを感じたわけではない。気づいたら己の腕が伸びていて、掌に髪の感触があって、智姫の頭を撫でる行動に出ていたのには、自分自身が一番吃驚していた。
「ななな、なに!?」
上擦った声と目一杯開かれた瞳と真っ赤に染め上がる顔面が自分を見上げていて、大いに戸惑っていて、逆に、やっている張本人には平常心が舞い降りた。もともと、こういう所作はお手の物だ。
手をのけようとするので一度かわし、再び撫で、むきになって払おうと動いたのが見て取れて、強めに掻き乱すように撫でてぱっと離した。
「頑張ってるおねーちゃんに、イイコイイコ。俺みたいに駄目兄貴なら肩の荷は軽くて済むんだけどな」
天衣無縫を装えば、一人照れ入っているのが恥ずかしいのか、雅司のノリに便乗してくる。
「駄目兄貴なんだ?」
智姫は小さな笑音を零す。まだ赤みが抜け切らないところは、正直可愛いと思う。秀司であれば一緒になって照れ入ってたかな、と想像して、あいつに「触れる」という行動がとれる筈もないか、と勝手に結論付ける。
「成績とか気にしてんの? 秀司は特別でしょ。てか、軽く化け物じみてるよね。部活びっちりやって首位独占し続けるなんて、人間技じゃないよ」
自分のことを駄目人間と称したのは、別に笑わそうとして卑下する言い方をしたわけではないし、気持ちを軽くしてあげようなんて道義があったわけでもない。のみならず、励まされるようなことを返されてしまった。
「化け物て…」復唱して、噴き出す。好きな者に使用する形容詞とは到底思えない。「成績とか別にしてもさ、俺は駄目兄貴。生活態度が優等生じゃねぇからな」
「自分で言う?優等生じゃないけど、手に負えない問題児でもないじゃない。女の子にだらしないだけというか」
「だらしない言うな。交友関係が広いと言うんだ。複数同時に付き合うとかしたことねぇし」
「だね」
知ってるよ、と頷く。
全面的に信用して雅司の話を鵜呑みにしているのか、無関心すぎて看過しているのか。確かめようかと惑い、無しだと結論する。好奇心だけで問うのは、止めておくに限る。ろくな結果を生み出さない。
「なぁ」
「んー?」
雑談に傾きかけているのを察知するが早く、智姫はすでに机上に意識を戻しつつある。さくさく物事を進めていくのだけを見ていれば普段通りに映るけれど、詩姫との悶着を気に留めていないのかと訝しむ。諸々含め確かめたくてここにいるわけで。
「そうやってさ、詩姫はおねーちゃんに護ってもらえっけど、そのおねーちゃんは誰が護ってくれんだ?」



