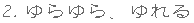
-9-
あの逃げ足の速さには賞賛を与えてもいいのではないか、などと馬鹿げたことを、雅司が去っていったドアを見つめて智姫は溜息を吐いた。自分に都合が悪くなると途端に姿をくらます。人には話し辛いことでも遠慮なく問うのに、だ。それでも周囲から疎まれないのは、才能と評価していいのかもしれない。
「能天気、ってわけでもないんだよ…ね、たぶん…」
独りごちて、自然と緩んでいた口端を引き締めた。溜息と共に、椅子に深く身を沈める。
他人事だから、面白そうだから、興味があるから聞いてるんだ。という姿勢を雅司はとっていた。その実、友人と心配してくれていると感じられた。おくびにも出してはいなかったけれど。
流説というものは往々にして尾ひれがつきやすいものと承知しているけれど、現状でどこまで一人歩きしているのだろうか。想像するだけで気が滅入る。が、もとはといえば自ら蒔いた種。
とはいえ、根も葉もないレッテルを貼り付けられるのは気持ちのいいものではなく。できるなら悪評が定着しないでほしい、と願うのは身勝手だろうか。
せめて自分の身近な人間には悟っていてほしいと願うなど、自嘲するほかない。
無意識に、雅司が触れた髪へと手が伸びた。毎朝百花にセットされる時とは明らかに違う、男の手。
秀司の手も同じくらいかな。
ぽん、と顔が浮び、ぼん、と音がしそうなくらい頬で熱が弾けた。それから、距離をとろうとした自分を思い起こし、落ち込む。
外はすっかり夜色に染まっていた。壁掛け時計を確認し、これくらい時間差をつければ夕食で詩姫と顔を合わせなくても済むと判断する。
生徒会業務に集中しようにも雅司が持ち出した話題のおかげで精神が落ち着かなくなっていた。ろくでもないミスをしそうな時は止めるに限る。帰ろうかと机上品の片づけを開始して、ドアがスライドする音がした。足音が聞こえなかったと思い返し、びくりと肩を揺らす。
霊的なものが見えたことはないけれど、存在は信じていたし、苦手の最高位に君臨するものだった。おそるおそる顔を上げ、存在を認め、脱力した。
「秀司…」
「まだ残ってたんだな」
違和感を感じた。
声の調子も態度も平常と同じ。けれど、あからさまじゃない怒りの片鱗が感じられる。
「帰ろうと思ってたとこ。秀司は?」
混濁する思考をいったん停止させる。一向に凪ぐことのない心情を現時点でどうにもすることもできず、雅司に依頼した本意じゃないそれにも一時蓋をする。
すべての感情や思考や意志を器用にコントロールできたなら詐欺師にだってなれるだろうか、なんてどうでもいいことを考えてみる。
「部活終わったの?…なんか、落ち込んでる?試合近いから緊張でもしてるの?」
正体不明の焦燥に急かされるままに並べ立てた。まったくもって落ち着きがない。
「ちーはすごいよな。俺らを絶対間違わない。親でさえ見分けつかないこと多いのに」
感嘆している、とは感じられなかった。淡々と述べる。抑揚がなく、違和感は濃くなる。
しかめっ面にならないよう笑みを模った。
「今更だね」笑ってみせる。誰に問われても返してきた同じ回答をした。「個々の人間だもん、違うでしょ」
目線を合わせないようにする為に、帰り支度に精を出す。無言で見つめられる視線には圧が感じられて、背を向けた。
このままの流れでいけば一緒に帰るのが成り行きというもの。それは避けたい。
言い訳をあれこれ思惟に没頭していると、気配が近づいたのが判った。背中に意識が集中する。
「ちーは、雅司が好きなのか?」
頭の芯が、震えた。
どういう経緯をもってその結論に達したのだ、とか、他の誰かに言われたとしても秀司の口からは聞きたくなかった、とか。様々な色彩の絵の具をぶちまけて掻き混ぜ原色が判らなくなるように、智姫の思考も錯雑する。
「きゅ…急に、なに言っちゃってんの?」
声が上擦って、滑稽に響く。激しくなる鼓動の奥に、厭な感触が蠢いていた。指先が震えていて、一度拳を握り締めた。
自分がいま、どんな表情をしているかなんて、想像もつかない。きっと、見せたくないものに違いはないけれど。
冷静な対応など何一つ思い浮かばず、どうしていいか判らなくなった時、人というのは笑おうとしまうものらしい。きっと、冗談にしてしまいたいのだろう。笑い声が零れ、失敗した。鏡がなくても大いに引き攣っているのが判る。
振り返って対峙しなかったのは幸いだった。
「……ちー、どうなんだ?」
声色が怖いくらいに真剣だった。突き刺さるほどの威圧を感じる。
逃げ出したくなって、金縛りに似た感覚に硬直する。浮んでは消える、逃げる算段の隙間に、なぜ秀司がそう結論したのか、の推測が割り込んだ。
「もしかして、さっきの見てた?」
浮んだのは雅司の軽薄な態度。頭を撫でられ、それを真っ赤になっていたなんて場面を見ていたなら、勘違いしてもおかしくはない。
「あんなの、雅司にしてみれば挨拶するのと同じなんだって。深い意味なんて無いよ」
いきなりのことに戸惑ったのは否定しない。かといって、特別な意識を抱くことはなかった。
動きを再開させて思考に没頭する。帰り支度を整えたら、もっともらしい理由を作って秀司を撒いてしまおう。じゃあ、次に考えるのは言い訳だ。と内側で行動を想定しようとして、思案の総てが弾けて真っ白になった。
ぬくもりが、窮屈ではなく、けれど力強く、智姫を包み込む。自分のではない腕が背後から姿を見せた、と思ったら、自身の身体が引力に従って少し後方へ傾いだ。
抱き締められたのだと判った時には、耳に秀司の吐息がかかる。



