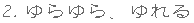
-10-
「ななななにとち狂ったことしてんの!?ふざけないでっ」雅司じゃあるまいし、というのを咄嗟に飲み込めた自分を褒めてあげたい。
振り解くわけにもいかず、金縛りみたいに身を硬くするしかない。心臓がかつてないほど大騒ぎしていた。風邪をひいた時でさえ無かったであろう急速な熱が顔面で弾けた。このままでは精神がもちそうにない。
「しゅっ…秀司、ってば。ふざけてないでよっ…お、怒るよっ!?」
「ちー」
肩口に顔を埋めるように俯く秀司から発せられる声の近さに、寂寞を連想させる声の音色に、背中がぞくりとする。
――男なんて抱きついてりゃおちる。
不意に、馬鹿馬鹿しいことを口にした雅司の台詞が掠めた。男なんて、を性別逆に置き換えて吹き込んだのではないだろうか。雅司と違って慣れていない秀司が、真に受けた可能性はゼロではない。
思いついてしまうと、それこそが答えに思えて仕方ない。
秀司の想い人が自分である、という雅司の戯言を一蹴したけれど、真実だったのではないかと仮定すれば、今の状況も理解できる。
こんなにも嬉しいことはない。だから、受け止められないのが、つらい。
「落ち着いて」
しー、と音が発せられ、暴れ狂う鼓動は収まりそうになかったけれど、凪いだ湖面のような秀司の声に、振り解こうとする動きを止め、表面上だけは落ち着きを取り戻す。背中越しに感じる秀司の気配の奥から、彼の鼓動の速さが伝わってきた。智姫に負けず劣らずの速度。決して冷静ではないのだと伝わる。
「ちー」静かに声を落とす。耳の傍で、吐息が智姫の髪を揺らす。「少しだけ、このままで」
震える真摯な声に抵抗できるわけはなく。噛み締める鈍重さで続きを紡ぐ。
「俺は…いつもこうなんだ。……いつも、ぐずぐずしているうちに、誰かに先を越されて、大事なことを指銜えて見ているしかなくなる。今回も、遅いのかもしれない。…けど、黙って諦めがつくまでじっとなんかしたくない。遅かったとしても、譲りたくないんだ」
なんの話なのだと、口を挟むことは叶わない。ぎゅっと目をつぶった。
「ちー、好きだ」
たぶん、現実では数秒の間。沈黙は、ありえないくらい長く感じた。しん、と静まり返った室内に、秒針の音が規則正しく刻まれる。
こちらから何かを言うのを待っている。催促するように、抱く腕に力がこもった。
はっきりと言葉にされて、気づいてしまった。
懸命に押さえ込んでいた気持ちが、本当に深くて、押さえ込むことも摘んでしまうことも不可能になっていたのだと。
「……そう」
どうにか捻じり出した声は、情けなく呆気ない単語だった。今尽力すべきは、平静を装い暴れ狂う鼓動を悟られないようにすること。特別な感情を持っていないのだと、呈すること。
「考えてみてくれないか?」
智姫の平淡極まりない返しをどう解釈したのかは不明だけれど、細かいところまで気が廻っていないのかもしれない、という印象はある。
……当たり前、だよね…。
人に想いを告げるという行為は、相当な勇気を必要とするものだから。
無言の空気に居た堪れなくなったのか、秀司は落ち着かない様子で「じゃあ」と囁いて、智姫を腕の中から解放した。
離れていく気配に、手を伸ばしたかった。同じ気持ちだと、伝えたかった。してはいけない、衝動。
強く拳を握り、自身の足をその場に縫いつけた。掌に爪が食い込む。その痛みに、ほんの少しだけ冷静な部分が顔をのぞかせた。
名前を呼んで、歩みを引きとめた。完全に振り返らない半顔の時点で告げる。
「秀司とは、付き合えない」
早々に出された結論を飲み下すまでに数瞬要し、落胆した。移り変わる秀司の表情を、智姫は真っ直ぐに見つめた。
「あたし…、付き合ってる人がいる」
もしも、と頭の片隅では考えてしまっていた。
もしも秀司の告白が早かったなら、自分はどうしていただろうかと。
今でさえこんなにも迷ってしまっている。結論は明白なのに。
自分が護りたいものの為に決めた後でさえ、こんなにも。
ばかみたい…。
これでいいのだと、思うしかないというのに。この告白のタイミングさえも、良かったのだと思うしかない。
そう、これでいいのだ。これで、描いた通りになれる筈だ。



