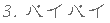
-5-
「よう、坂巻」友好的に、をイメージして見事失敗している声だ、と見上げた先にあったのは、智姫の周りにいる数名と遜色ないくらいの柄の悪さを纏った、制服を着崩した男達。手前に立つ男が、鋭い眼光を坂巻に向けている。
何が始まるのか、なんてわざわざ訊かなくても想像に容易い。
やばい、と自身の内側で警鐘が鳴った時には、目の前で殴り合いが始まっていた。入り乱れ、揉み合い、蹴り合って、倒れて。衝突音と、誰のものかも判らない悲鳴と、怒声と。
気づいたら、少し離れたところで、尻餅をついていた。遅れて、拳が飛び交う直前に弾かれたのだと思い出す。
坂巻と一緒にいたことは知られている。ここにいては危ない。警鐘が鳴る。煩いくらいに鳴っている。脚が震えていて、身体中が震えていて、立ち上がるだけの力が入らない。
坂巻を殴り飛ばした一人と目が合った。第一声を放ったその男は、薄っすらと笑みを浮かべた。獲物を追い詰める獣のように、じわりと近づいてくる。
額から流れている血の赤が鮮明すぎて、傷など意に介さない笑みに、恐怖する。伸びてくる腕の陰が顔にかかった。距離を縮める男の陰が、智姫を覆いつくす。
容赦ない引力が生じた。髪を鷲掴みに持ち上げられたのだと判った時には、横っ面に熱を感じた。激しい痛みが脳内を乱す。
抵抗を試みているらしい己の手が、視界の中で滑稽に揺れていた。追い払おうと、抵抗しようと、ゆらゆら、ゆらゆら。
その向こう側に白光が一筋輝いた。蛍光灯の光を受け、刃が怪しく光る。一閃し、強烈な痛感と共にあった頭部の引力から解放される。床に落ち、視界の端にぱらぱらと舞う筋を捉えた。糸くずより細い、真っ直ぐな糸状の束がばさりと、床に伏した智姫の面前に落とされた。
詩姫が羨ましいと梳いたもの。百花が楽しいと言って触ったもの。少しでも女の子らしく見せたくて、大切に伸ばしてきたもの。本当のきっかけは、好みだと聞いたからだった。
おそるおそる触れる。不格好に軽量感を知らしめる片側を。あるべきものが失われていて、血の引く音がした。ぐらりと視界が揺れる。
蛍光灯が翳り、首をよじる途次に、二本の足が見えた。
「あいつは所詮、誰も守れねぇ。繰り返すだけだ」
背筋が凍るほどに冷徹な声は、智姫ではない方角に向けられていた。更によじり見上げる。靴底が見えた。二本の内の一本が、風を切って振り上げられている。
痛みを想像し、身構える。目が離せなくて、黒々と己を狙う靴底を見つめた。
蹴り落としの開始の動きが見え――智姫を覆っていた翳りが消えた。一瞬、蛍光灯の光が視界を白に染め、反射的に目を細めた時には別の陰が智姫を覆った。
「坂、巻…?」
唇を動かすと口端が痛んだ。
怒りに満ちた表情のまま、男を殴った手で智姫の二の腕を掴む。引っ張り立たせようとしているのだと判っても、身体は力を失っていうことをきかない。坂巻の支えを借りてどうにかへたり込む格好まで起き上がった時、坂巻の背後に影が立つ。自身に降り掛かるそれを察知し、素早く振り返った坂巻の向こう側に、拳を振りかざす姿があった。
悲鳴を上げる間もなかった。世界が反転したのかと、思った。
鋭く吐き出すほどの短い呻きが漏れ、それが智姫を庇って殴られた坂巻のものだと判る。再び尻餅をついた智姫に倒れ込まぬよう耐える坂巻は、痛感が引かぬ内から上半身を起こし翻ると、男に突進していった。
混沌とした時間がどれくらい流れたのか、現場からどうやって遠ざかったのか。気づいたら、小さな公園のブランコに座っていた。薄闇に閉ざされた人気の無い場所で、一人だった。
錆びた鎖が動きに合わせて鳴いている。漕いでいるわけでもないのに、と見遣り、自分の手が震えていることを知った。次第にはっきりとしてくる記憶に、恐怖が這い登り、唇までもが震え出す。目の奥が熱く、嗚咽を殺しながら、泣いた。
風に吹かれた髪が揺れ、片側が失われた現実に、涙が止まらなくなる。
そうして、身体が芯から冷え切った頃、ようやと周囲に目線を置いた。携帯電話を取り出し、無事機能することを確認し、電話帳を開いた。が、そこから先、指を動かせなくなる。
誰に電話すべきか、感情と理性が交差する。たっぷり躊躇った挙句、感情よりも理性を優先させることに成功した。
コール音が静寂に霧散する。十回を越え、数えるのを止めてしばらくして、耳から離した。通話終了ボタンに指をかけた段階になって、相手が慌てた様子で出た。
「もっ…もしもし!?智姫っ?」
部屋に置きっぱなしにしてて出るのが遅くなった、とか何とか、漏れ聞こえてくる。じっと見つめているうちに、また視界がぼやけてきた。
そういえば百花も怒らせてたんだっけ、と思い出す。
もしもしを数回、名前を同じ回数くらい呼ばれ、鈍重な動きで耳にあてた。息吐く間もないくらい継続されている。
涙声を飲み込んで、深呼吸した。
「……百花」
ひどく暗い声音になった。電話口の向こうで、百花が息を詰める。智姫の様子がおかしいことを察知している。震える呼気を吐き出して、依然トーンは低いまま、続けた。
「あたし、思い上がってた。自分のことも…誰も…護れないんだって、判った」
最良と信じてやってきたことの総てが、間違いだったのかもしれない。残ったのは、周囲を傷つけた事実だけ。
「智姫っ?今どこにいんの!?」
緊迫した百花の声が、沁みる。
「――…百花……助けて…」
搾り出して、あとには嗚咽を零すしかなかった。



