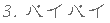
-6-
人の陰に隠れる。といっても、実際のところ完璧に姿を消せるわけはなかったし、智姫の前を行く百花の背中にすっぽり隠れられるわけもなく、結果、珍妙な列車ごっこみたいな体勢となっていた。
「いい加減、歩きづらいっての」
痺れを切らした百花が振り返る。ほら、と言って腕を掴み、自分の横に引っ張り出した。校門を通過したばかりの位置で、登校する生徒の姿は多い。
「余計目立つって」
「そんなこと言ったって…」
「気に喰わないっての?」
「そうじゃなくて…。本当に似合ってる?変じゃない?」
自信満々の百花はいつものことながら、ここまでしどろもどろになる智姫は珍しい。注目が集まるのは身を隠そうと奇矯な行動をとっている智姫の様子の所為ばかりではなかった。
誰もが一目で判るほどの変化。単なるイメチェンならば堂々としていればいいものを、彼女の様子を見ている限り、そうは判断でき兼ねるというもので。
驚愕と表現できる視線の集中砲火に、逃げ出したくなるのをじっと堪えた。ここ最近の話題喚起の張本人となってしまっている不本意な現実に、拍車が掛かっているのをひしひしと感じる。
「似合ってるって。メイクもばっちりなんだし!」
「そこだよ!ここまでしっかりする必要なかったって。巧く隠してって言っただけなのに…」
これまでメイクなんてものには縁がなかった。私服で出掛ける時に、詩姫がのせてくれる色付グロスをつける程度。それさえも無理矢理感は否めず、基本すっぴん。
美容師を目指す百花はメイクの勉強にも勤しんでいる。普段自身に施しているのは、ぱっと見判らないくらいのナチュラルメイク。智姫の仕上がりもそうなるものと勝手に思い込んでいたら、あれよという間にフルメイクが完成していた。これでも薄いくらい、やり直しなんてしないからね、と断言されてしまえば、どうしようもなくなった。
確かに派手にはなっていないしナチュラルに近いのだろうけれど、とにかく見慣れない所為か違和感がある。
「だってさぁ。やってる内に楽しくなっちゃったんだもん」
本音はそこか、と心の内だけで突っ込む。
「アイメイクは必要だったわけ?」
「バランス、ってもんがあるの。全体的にやんなきゃ、変になるだけだって。隠したいとこに注目集める破目になるよ?」
ちらりと想像してみて、そういうものなのかもしれないと納得。結局、百花には逆らえない。お願いをしたのはこちらなのだ。
昨夜は百花の家に泊まった。深夜遅くまで散々話を聞いてくれた挙句、今朝登校できるまでに一役買ってくれたのだ。文句を言えば罰が下ってしまう。
「はよーっす!」
声の主がぽん、と浮び、反射的に顔を背けた。背けた先に、顔を合わせたくなかった上位にランキングしていた人物までいて、一気に顔が引き攣った。
最上兄弟が揃って登校するなど、稀有すぎる。妙な汗が滲み出そうになる。
百花の隣にいた見慣れぬ後ろ姿の正体が智姫だと判明した秀司もまた、まじまじと智姫を見つめたまま立ち止まった。
挨拶を投げ掛けた人物――雅司は顔が確認できる位置まで移動し、智姫と確認して、半開きの口を開けたまま、数秒静止。潜水から浮上してすぐ酸素を取り入れるが如く大きく息を吸い込むと、地声の倍はあろうか音量で素っ頓狂に名前を呼んだ。ご丁寧に指まで差して。
目の前にある手を叩き払い睨み付けた。こうなりゃ開き直るしかない。
「なんか文句あんの!?」
無意味に攻撃的になってしまった。自分でも見慣れないメイクや髪型に、羞恥心がはちきれそうになる。
「なに怒ってんだよ」
雅司は癇癪を起こした子供に呆れるように笑う。彼が驚いたのはほんの数秒のことだけで、持ち前の順応性の早さから、すでに普段の調子を取り戻している風だった。依然智姫を凝視しているのは秀司だけ。
「ずいぶんバッサリいったもんだよなぁ。これって百花がやったの?」
どっちに感心しているのか判然としない言い方をする。あるいは両方か。
背中の真ん中くらいまであった長髪はベリーショートに変貌した。乱闘で失った片側は耳の後ろあたりで、ショートボブくらいにはできるとした百花に、思いっきり短くしてほしいと頼んだのだ。
「そう。似合ってるでしょ? 智姫のイメージ通り」得意気に百花は胸をはり、
「今までが悪かったみたいに言わないでよ」泣きそうな心境で智姫は言う。
「長いのもよかったけど、これもありだな。…な、シュウ」
ふられて、ようやと意識の舵を取り戻した秀司は、改めて智姫を見る。目が合い、気まずさに後ずさりする。戸惑いながら同意されても、逃げたい心地は一向に鎮まらない。それでなくても告白を断った経緯があるというのに。
百花を促して駆け出そうかとよぎり、唐突に秀司に腕を掴まれ、小さく悲鳴を上げた。
「な、なにっ?」
「わ、ごめん」
ぱっと解放し、秀司は再度謝った。そんなに謝ることでもないけど、と思った次の瞬間、二度目の謝罪は次なる行動の前ふりだと知る。
「この痣、どうしたんだよ?」
僅かに怒気を孕んでいた。なのに、頬に触れる指先は優しくて。近距離に近づいた秀司の顔に、鼓動が暴れ出す。
「痣?」
しらを切り通すしかない。メイクで隠したのは完璧の筈だった。どこを殴られたのか知っている智姫でさえ見つけられなくなるほどに。百花も驚いている。
秀司の手からも視線からも逃れ身を翻す。喰って掛かろうとする秀司を遮ったのは、閉門を終えた教師が生徒達を校内へと急がせる指示。
「ちー!」
強制的に話を打ち切って玄関に向かおうとした足が止まる。秀司の余裕のない声に、動けなくなる。
平常心、の表情を貼り付けて振り返る。真摯な視線が痛いくらいに突き刺さっても、崩さないよう懸命に保った。
「試合、見に来てくれるよな?」
約束していたことを思い出す。けれど、あの時とは状況が変わってしまった。友人であることすら、やめようとしているのだ。
はっきりと首を振る。「行けなくなった」
ごめん、は飲み込んだ。約束を簡単に反故する人間だと、軽蔑してくれればいい。嫌われたならきっと、この想いも消滅させることができる。
「友達で、いてくれるだろ? だから…友達としてでいいから、試合きてくれよな」
優しい秀司がどんな想いで口にするのか。どこまで自分は、傷つけていくのだろう。
返す言葉を失って、立ち尽くす。動き出した秀司は俯いたまま、もう目を合わせようとはしなかった。
鞄を持つ手に力が入り、擦れ違いざまの秀司の呟きに、泣きたくなった。
――告白は無かったことにして。ごめんな。
確かにそう、呟いた。



