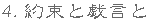
-1-
家の中に、人の動く気配がする。外はまだ、活動を始めるには早い時刻。物音も話し声も遠ざけたくて、智姫は頭まですっぽりと布団を被っていた。朝日を遮断した暗闇の中で、膝を抱えて小さくなる。
階下では母親と詩姫がひそめた様子で動き廻っていた。寝ている者に対する配慮なのだろうけれど、はっきりと目覚めている智姫にはどんな動きをしているのか手にとるように判る。
試合当日、マネージャーである詩姫は朝早く出発する。
ここ最近ろくに口もきいていなかったけれど、昨夜は険悪な空気さえ流れていた。怒り心頭な様子の詩姫に話かけられるだけの意気を起こせなかった。そんな詩姫の態度を両親は大事な試合の前でピリピリしているのだと解釈していたようだった。
悶々と闇に閉ざされているうちに、玄関が開く音が聞こえてきた。いってきます、と音量を絞った詩姫の声がする。扉が閉まり、静寂が室内を満たした。足音が遠ざかっていく、を予測して、それがないことを訝しむ。代わりに、話し声がした。
声が遠すぎて、詩姫のですら判別できないほどに聞こえづらい。会話はすぐに終了したらしく、足音が一つ、去っていく。
闇に身を委ね、包み込むぬくもりに沈む。唐突に割り込んだ携帯電話の振動音に、びくりを身を強張らせた。こんな早朝にかけてくる可能性のある人物が浮ぶ。
見当違いの謝罪をさせてしまった秀司の、切なく歪む顔を思い出す。
着信が止む。数秒と開けず、再び振動を開始する。無視しようにも続けて三度繰り返されれば、痺れも切れる。携帯電話の小窓で明滅する名前を確認し、肩透かしをくらった気分に陥った。
通話ボタンを押し、耳にあて、けれど無言でいた。
「はよーっす。出掛ける準備はできてっか?」
ほとんどの人々が寝ている時間帯にかけておいてその問い掛けはおかしいでしょう、という突っ込みをする気も失せる。能天気な雅司の顔が脳裏を掠め、一気に脱力。
「出掛けるの前提な根拠を述べてよ」
「試合見に行くぞ」
人の話を聞け、と叱りつけたくなる。
「行かない」
間髪入れずに返す。
行く気は無かった。仮に行く予定だったとしても、観戦者がこんな時間から行く必要は無い。非常識だと諫言しようかと思い、糠に釘の結果が浮び、やめた。無駄なことに労力を注ぐ気力がない。
「さっさと準備しろ」
言うや、通話終了の電子音がした。だから、人の話を聞け。
放置決定。次にかかってきても無視すればいい。床に置きっぱなしにしてあるクッション目掛けて携帯電話を放り出す。再び布団の中で蹲っていた。
数分後、携帯電話が震えた。取りに動こうともせず無視。しばらくして、今度は窓ガラスに微細な衝突音が聞こえてきた。はじめは風に飛ばされた塵芥がぶつかっているのだと思った。けれど音は止むことがなく、定間隔ですらある。人の仕業、と判断するのが自然で。
さきほどの、外の様子を思い出す。詩姫は誰かと話をしていた。
勢いよく布団を撥ね退けカーテンを開ける。予想通りと言うべきか、雅司が振り仰いでいた。電話口の口調と寸分違わない、能天気な笑みと対面する。
多少の距離をものともしなくて済むように、大袈裟なくらい溜息を吐く。ガラスが白く曇った。クッションの上で、携帯電話が震え出した。窓の外、雅司が持つそれは脇にぶら下がる手に握られている。今度こそ秀司かとよぎり、雅司が電話を耳にあてた。据えた睨みを降ろして、クッションから電話を取り上げる。
「準備しろっての」
「行かないっての」
「わざわざ迎えにきてやったんだ。行くぞ」
「頼んでないって」
端的に返し、そういえば、と思う。
そういえば、雅司が試合を見に行くのは初めてじゃないだろうか。部活を辞めて以降関わりを持っていなかった。興味(そもそも、あったか怪しいものだけど)が無いことには首を突っ込まないタイプだった筈。
「準備しないなら着替え、手伝おっか?」
どんな脅し文句だ。呆れて物が言えなくなる、のをぐっと堪えた。
「こなくていい」
「じゃあ、さっさと準備しろ」
またもや通話は強制終了。仕方なく、のろのろと開始することにした。



