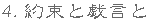
-4-
井ノ瀬が選んだのは、自動販売機が並ぶ休憩コーナー。その中の一つに智姫を座らせるとドリンクを購入して向かいに座った。ペットボトルを開栓するや大きく喉を鳴らして一口飲んだ。盛大に息を吐き出し、ついと智姫に目線を合わせる。
「戻らなあかん、じゃなかったの?」
「ちーの悪いとこは、すぐ我慢することやな」
藪から棒に、何の話なのだ?
浮んだ疑問を差し挟む隙を与えず、井ノ瀬は続けた。
「いや、我慢ちゃうか。ほしーもんがあって、それを譲れないって熱があって初めて、我慢て言葉が成り立つんやろ。ちーのは、単なる諦めや」
どきりとした。真摯すぎる眼差しからの逃げ道を捜す。
「唐突に意味判んないこと言い出さないでよ。試合前で緊張でもしてるの?」
揶揄の言葉に対して返されたのは、溜息だった。
「無自覚、なんかな。益々たち悪いやんか」
語調は軽やかに紡がれるのに、じわりと追い詰められる圧迫感がある。口を閉ざすのは良策ではないと内側がささやきかけるのに、対抗する言を持ち合わせていなかった。
井ノ瀬には確たる何かがあるようで、旧友ゆえの無遠慮さがある。
「例えばや。こーんなちっさな時やったら、自分が望んだものをいつもいつも譲ってもらえても、ほしーもんが手に入るから、欲求が満たされたことに満足して他は気にならんかったりするやろ?」
床と水平にした掌を身体の横に出し、テーブルよりも高い位置で静止させた。背丈を示しているのだとすれば、幼かった頃を意味する。おそらく、知り合ってから転校するまでの頃を示しているのだ。
「けど成長してけば、そんな単純な感情だけで片付けちゃいけないことがある、ってことや」
「なにが、言いたいの?」
「詩姫と話した。俺が知ってる頃から、変わっとらん。そう思った。変わらんことが悪いとは言わん。けど、変わらなあかんこともある」
詩姫から、どんなことを聞いたのだろうか。想像するしかないけれど、難くない。
いつそんな話を、と問おうとして、やめた。この試合会場でないことは確かで。同窓会の連絡をしてきた以降、繋がっていたのかもしれない。
「譲り癖は直っとらんのやろ?」
「――あたしは別に…。なんでもかんでも詩姫に譲ってるわけじゃ、」
「覚えとる?学校でやったアクリル工作」
記憶を探る。時を遡り、現在目の前にある井ノ瀬の無邪気な笑みが、過去とだぶる。
「切ったりくっつけたり色つけたりしたやつ?」
正解、とクイズの出題者みたいな言い方をする。
「ちー、男子にもらったやんか。クラスん中でも、いっちゃん巧い出来の。みんなが羨ましがって」
「……あぁ。あったかも、ね…」
曖昧にする智姫に、はっきりせぇへんな、と井ノ瀬は笑って、続けた。
「詩姫がそれ、ほしがって。あん時、ちーは厭やって、言ったな? どんだけ詩姫がほしがっても、譲ろうとしなかった」
曖昧にしたのは、思い出せなかったからじゃない。はっきりと覚えていたからこそ、だった。
空気を沈ませた智姫を見て、井ノ瀬は明るく笑音を洩らす。
「それな、なんも、悪いことちゃうで?もともとはちーがもらったもんなんやし、ほんのちょこっと早よう産まれただけのお姉ちゃんやのに我慢せなあかん、てのがおかしいやんか」
「……違う。そうじゃない」
詩姫がほしがったものをあげたくないと言った。それだけで、今の智姫は出来上がらない。
「覚えとったんか、やっぱり」
井ノ瀬は呆れたように息を吐く。
「やっぱり?」
「詩姫も、覚えとったで。あれはちーの所為やない。…そう、言っとった」
「……詩姫、が…?」
内心を有り体に、表情を曇らせた。逡巡に呼応するように、瞳が揺れる。
「ちーは悪ない、ゆーとるやろ?」
井ノ瀬のトーンは変わらない。笑顔が、無邪気さが眩しくて、思い返しては罪悪感に襲われて、俯く。
「…ほしい、って言われた時にあげてれば、あんなことには…ならなかった」
「それや」
明朗な声につられ、弾かれるように顔を上げた。それこそが解答だ、と顔に書いてある。
穴があくほどに凝視しても、彼の言いたいことが見えてこない。首を傾げるしかなかった。
「そこから、始まっとる。ちーの諦め癖。無意識に近いのかもしれへんけど、始まりはそこや」
いつもであればすんなりと欲しいと言ったものが手に入るのに、あの時ばかりは手に入らなかった。意地でも譲ってくれない姉に、妹も意地になった。強引に取り上げに動き、それをかわそうとした智姫の腕があたり、詩姫はバランスを崩した。
教室の隅で繰り広げられた意地の張り合いは、妹が壁に衝突するという形で打ち切られた。
「あの子、傷痕残ってるの。女の子なのに…」
下唇の真下を切って、今でもそれは残っている。間近で見なければ判らないほどの小さなものだけれど。
「ちーは悪ない。詩姫もそう言ってる。そこまで気にすんのはかえって相手に失礼やで」
だけど、と言い差して、飲み込んだ。どう反論すれば自分の気持ちを判ってもらえるのか、どう整理すればいいのか、判らなかった。
幼い頃の話だから、あれ以降蒸し返されることのなかった話題だから、詩姫は忘れているものだと思っていた。
「ちーの本心を、ぶつけてほしかったんやないのか?」
「……本心?」
「譲れんもんは譲れん、って。…あん時みたいにな。自分に遠慮してほしくなかったんやろ」
かぶりを振った。判らなくなっていた。それは本当に、詩姫の本音なのだろうか。
彼女は姉を、恨んではいないのだろうか。笑顔の裏に、慕ってくれる顔の奥底に、隠された本心に触れるのが怖かった。本当はずっと、自身に傷を残した相手を嫌っていたのだと告白される日を、恐れていた。
井ノ瀬が言いたいことを言いきった時、彼を捜していた仲間が試合会場へと連行して行った。気を揉んだ部員の剣幕にどこ吹く風で、去り際、床を睨み据えていた智姫の頭に手を置いて断言した。
――智姫に傷つけられたって、思ってない。絶対や。
井ノ瀬を信じられないわけではない。でも、鵜呑みにもできない。あの時から燻ぶり続ける疑念は、容易に消滅しないもので。
確かめなきゃいけない時機にきているのかもしれない。逃げるのは、終わり。
ぎゅ、と唇を噛み締め顔を上げた。窓の外は気持ちのいいくらいの青空が広がっている。井ノ瀬の軽やかな断言が幾度も蘇り、空の爽快な景観と重なり、後押しされている気分が沸き起こる。その蒼穹の下、動く影を視界に捉えた。影をしっかりと捉えられる角度に首を動かし、混乱した。
「え…?」
どうして? 呟いた直後、駆け出していた。
勢いに負けた椅子が倒れる音が背後でしたけれど、そのまま放置した。



