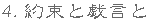
-5-
仇にぶつけるほどの殺気立った声音を放っていた。自身の声に、驚く。それ以上に驚いて智姫を見つめているのは、智姫が大切したいと願う存在。建物を飛び出して目指す二人がいる場所まで辿り着き、ひったくるように詩姫を背後へと廻した。一連の様子を微動だにせず見ていた坂巻を睨みつける。智姫が登場した瞬間だけ瞠目し、それから岩永と同様の表情になり、それを掻き消した。
ちーちゃん、と声がする。見なくとも、詩姫が怯えていないのが判った。校内に乗り込んできた坂巻に絡まれていた時とは明らかに違う空気を感じられる。訝しみながらも、優先すべきは他にある。坂巻から目線を外さず、後方に声をかけた。
「詩姫、戻って」
「ちーちゃん」
詩姫の声は、芯のあるしっかりしたものだった。本当に怯えていないのだと確信が持て、安堵する。き、と坂巻を睨み据えた。
「なんなの、こんな所まで来て。詩姫に近づかないで」
無表情だった坂巻の口角が持ち上がり、鼻白んだ。
「約束した覚えはねぇ。お前見てっと、苛つき越して憐れになってくるな」
なにを言うつもりなのだ。詩姫のいる、この場で。
止めなければ。聞かれるわけにはいかない。目の前でわざとらしい憐憫の目を向ける坂巻が、まるで敵に思えた。
「詩姫」
「でも…」
こんな険悪な雰囲気の中に置き去りにするのを気兼ねするのも判る。判るけど、これは智姫が解決すべき問題なのだ。
「お前さ、あれもこれも護ろうってのが、そもそもの間違いなんじゃねぇの?」
本当に、なにを言うつもりなのだ。これ以上口を開かせては駄目だ。
智姫が坂巻に近づいた理由。――それを詩姫に聞かれるわけにはいかない。
けれど坂巻には、智姫の警戒を覚った上で、止める気がないらしい。
「厭な思いすんのは自分だけでいい、って?偽善だな。単なる自己満足でしかねぇ」
「黙れっ!!」
思わず、声を荒げていた。詩姫が、びくりを身を強張らせる。半顔で振り返り、妹の戸惑う顔が視界の端に入る。自身の余裕の無さに遣る瀬無さが込み上げた。
今でなくても、詩姫は知ろうとするだろう。智姫と坂巻の関わり合いを。他の誰かから聞かされるくらいなら、己の言葉で伝えたい。
意識して、声音を和らげた。
「ここはいいから、行って。あとでちゃんと話すから」
「ちーちゃん…」
「マネージャーはさ、みんなを支えるのも仕事のうちだよ。詩姫の役割でしょ」
そうだ。だから、自分は自分の役割を果たさなければいけない。
詩姫の責任感を刺激することを言えば、渋々でも了承してくれるかと期待したのだけど、返ってきたのは予想外のことで。
「……じゃあ、ちーちゃんのことは、誰が支えるの?」
切羽詰まる声。今にも泣き出しそうな。
「し、詩姫…?」
妹を泣かせようとしているのは、誰?
悲しませているのは、誰…?
「ちーちゃん、あたしねっ…」
意を決した切迫した詩姫の声と、彼女の名を呼ぶ声が重なった。数メートル離れた場所にユニフォームを着た長身の影がある。部のキャプテン、船渡沙月だ。
秀司が高校を決めた理由。彼が敬慕するバスケプレーヤー。
詩姫が選んだ高校でなければ、智姫は今の高校を選ばなかった。沙月がいなければ秀司も選ぶことがなかった。
そして、入試の時、席が隣にならなければ、消しゴムが無くならなければ、声をかけることはなかった。
偶然の重なり合いが導き出した現在。
出逢わなければ、こんなにも切ない想いを抱えることはなかった。でも、出逢ったから、知ることができた感情もある。
枝分かれした道を選択してきたのは、自分。責は己の中にある。
後ろ髪引かれる様子で去っていく半身を見送っているうちに内側に芽生えた決意は、坂巻に対峙する時には強固なものとなっていた。
「余計なこと、言わないで。あんたの近くにいたことは、あの子には関係ない」
存分に睨め付けているつもりなのだが、坂巻には痛くも痒くもないらしい。
「無関係とは言い切れないだろうが。俺になんつった?」
見張ると、言ったのだ。それ以外に理由はないと、断言した。自分の女しか傍に置かないというのなら、なると言った。
いつ現れるかも判らない存在に神経を費やすより、効率がいいと思ったからだ。付き纏って、疎ましいと思わせることができたなら、最善だと思ったから。
護りたい存在を、危険なことから遠ざけられるのなら、何だってするつもりだった。
そして、秀司とは百八十度違う人間と付き合ったと示せれば良かった。詩姫が気兼ねすることなく好きな人に素直になれるなら、それで良かった。
「あの子には、知らせる必要のないことなの」
話さなければいけない局面にきている。それを坂巻にさせたくなかった。自分の口で説明したい。詩姫にもそう、約束した。
「でも、やめるから。あんたとは、二度と会わない」
「勝手にしろ。俺も、勝手にするまでだ」
言外に、何をするか判らないがその覚悟があるならやってみろ、とあった。
智姫が見張ると言った時と同等の、不敵な笑みが坂巻に浮ぶ。それを睨みつけたまま、そっと深呼吸した。
「どうとでも、仕掛ければいい。あたしは、負けないから。こんな方法であの子を護ろうとしたのが、間違いだった」



