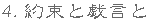
-7-
「し…試合、は?」整理もつかぬまま、これこそが優先事項とばかりに口にする。口にして、大事な試合だと言っていたのに巻き込んでしまったことに懺悔したくなった。集中を乱すことをしでかした事実に、今更ながら申し訳なさでいっぱいになる。
「ごめん。早く戻って」
「ちーちゃん!」
一度は去った筈の姿を視界に捉える。妹は怒っていなかった。ただ、心配してくれている。沁み込むようにそれが感じられて、涙腺を刺激する。
間近に迫った妹を直視できなくて、でも、俯いてしまっては涙が零れてしまいそうで。結局、不安げに見つめ返した。
「ちーちゃん、あたしね」智姫の両手を詩姫の手が包む。「知ってたんだ」
詩姫と、真正面からまともに目を合わせたのは怒らせた以来で。憤然としたものをぶつけられると覚悟したのも、杞憂に終わる。
穏やかすぎるくらいの語調に面食らい、遅れて、言葉の意味を咀嚼した。
「知って、た?」
自分と同じ造りの顔がゆっくりと頷く。
「ちーちゃんが、あたしの為に動いてくれてたこと。あの人の所に一人で乗り込んで行った理由。関わってないって、嘘ついてたことも。……全部、判ってた」
穏やかで、ともすれば微笑みすら浮んでいるように映る。怒っていないのかと胸を撫で下ろしかけて、詩姫の表情が一変した。
「どうしてそんな、危ないことしたの?」
静かだが、確実に諌める響きを持つ声音。条件反射が如く、身構える。やはり怒らせているのだと焦る気持ちが湧いて、慌てて口を開いた。
「危なくなんてないよ」
坂巻に危害を加えられたわけではない。原因ではあるけれど。
怪我をしたのも、髪を切らざるを得なかったのも、自らの蒔いた種だと自覚すれば、後悔するのはお門違いというもので。
「あたしは、ちーちゃんを護りきれなかったあの人が憎いよ」
「……詩姫、どこまで知ってるの?」
ふと沸いた、恐れと呼べる不安に煽られる。経緯を知ってる者から聞いたのではないだろうか。
「もっと早く、ちーちゃんを止めなかった自分が憎い」
詩姫は智姫の質問には答えない。それで、確信めいたものが芽生えてしまった。
詩姫は聞いたのだ。それは、百花からではない。彼女でなければ、残された解答は絞られる。
「もしかして…坂巻から?」
言も、頷く所作もなかった。故に、肯定を示していると判った。
「会ったの!?」
一体、いつ会ったのだろう。百花は智姫が話すまで知らなかった風だった。ということは、それよりも以前に一人で赴いたのだろうか。
どうしてそんな危ないことを、と言いかけて、止まる。これでは鸚鵡返しだ。智姫が気づいたことによって、詩姫は満足そうに表情を緩めた。
「同じなんだよ、ちーちゃん。それとも、自分だけは危ない目に遭わないとでも思ってるの?」
かぶりを振った。
想う気持ちがあるからこそ、心配するし、怒るのだ。一方方向しか見えていなかったことに、ようやと気づかされていた。
「たった数分の違いだよ?あたしだってちーちゃんの為になにかしたいよ。頼りなくても、ちーちゃんを護りたいよ。あたしだけが護られるべきだなんて、どうかしてる」
「…うん」
返す言葉もありません。最近、こんなのばっかりだな、と苦笑するしかない。
「それにね」
詩姫の追撃は収まらない。言いたいことを、ここぞとばかりにぶつける気らしい。
他にもあるとは微塵も想定しておらず、再度身構えた。脳内では急いで思い当たる節を捜索しているのだけど引っ掛からない。
「ほしいものはほしいって、言って」



