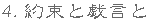
-8-
「え」井ノ瀬の顔がぽんと浮ぶ。今頃コート内を駆け廻っているのだろうか。
「譲りたくないものは譲らないって、言ってよ」
「それは…」
「言っとくけど、ちーちゃんがあたしに引け目感じることなんて、なーんにもないんだからねっ」
数年振りに再会した同級生の断言は間違っていなかった。気にする必要はなかった。井ノ瀬が言うように、負い目を感じる必要はなかった。
「判った?」
勢いに圧されて、咄嗟には返事が出来ずにいた。
普段ののんびりした妹とは掛け離れた態。自分が投影されてるようで、もとは一つだったんだなと思う。
念押しで同じことを言われ、圧されるままに頷く。詩姫は満悦そうに笑い、それから、呆れたように息を吐いた。
「だいたいね、シュウちゃんを好きだって匂わせれば焦って動くかと思えば身を引いちゃうし。苦労が水の泡」
「へ…?」
詩姫らしからぬ発言が聞こえた気がする。我が耳を疑うも、遣り取りを見ていた秀司もぽかんとしていた。空耳じゃないらしい。
「あたし、シュウちゃんをそういう対象に見たことないよ」
ぽかん継続中。どれもこれも、そう見せようとしていただけ、ということ?
「言ってほしかったの。気になる人がいるならいるって、相談してほしかったの。なんでもかんでも譲ってくれても、嬉しいのは本当に小さい時だけだよ。――対等に見られてない気がして、ずっと厭だった」
そんなつもりはなかった。けれど、誤解を招いたのであれば、問題があったということだ。
「判ってるよ」詩姫は言う。清々しいほどの微笑みで。「ちーちゃんが悪いわけじゃないよ」
「ごめん…」
それでもやっぱり、自分が悪いのだと思う。いつの間にか、姉であることに執着しすぎていたのかもしれない。
「ちーちゃんは悪くないってば」笑みを深くし、秀司に目線を移す。「というわけで、先行ってるから。開始までにはきてね」
スターティングメンバーである秀司を置き去りに詩姫は行ってしまった。爽やかな去り際に、残された二人は呆気にとられたまま見送るしかなかった。
「え、っと…。戻った方が、いいんじゃない?」
会場の方角を指差す。詩姫はああ言ったけれど、色々と整えることもあるのではないだろうか。ウォームアップだったり、メンタル面だったり。
「そうだな」
秀司は煮え切らない返事を寄越す。坂巻に向けていた勢いもすっかり削がれ、戸惑っていた。
「秀司?」
「…からっきし対象外とか言われんのも、ちょっとヘコむな。同じ顔なだけに、ちょっと…」
今度は自分が、といった風に秀司は乾いた笑いを零し、けれど間に流れる気まずい空気は気まずいまま。
「ジャージの彼は、知り合いなんだよな?」
「ジャージの、彼?」首を傾げ記憶を探る。「あ、ノセのこと?…ほら、前に同窓会の話したじゃない?あれの幹事役を買ってでた人」
思い出したと声にして、秀司は黙り込んだ。
「ノセがどうかした?」
「仲いいんだなって、思って。おかげで集中できなくなった」
頬こそ膨らまないまでも、不貞腐れているようで。智姫の視線を感じたのか、秀司は慌てた。
「って、こんなこと言われても困るよなっ…」
乾いた笑いが短く吐き出され、唖然と向けられる視線から逃れるように、くるりと智姫に背を向けた。
「俺、行くなっ。じゃ、じゃあ!」
「秀司っ」
秀司が駆け出すよりも早く、背中に抱きついていた。焦りが引き出した、ほぼ無意識の行動。冷静であったなら、絶対にやってない。
背中がおおいに強張る。凝固し、心音が離れている人にまで聞こえるのではないかというくらい暴れているのが伝わった。
上擦ったどもり調子で秀司が名を呼ぶ。智姫もまた、暴れ狂う己の心音と闘いながら、ぎこちなく反応を返した。
秀司の想いはまだ、残されているだろうか。
遅いのかもしれない。傷つけた分、嫌われている可能性はある。助けにきてくれたのは、友人として、だけかもしれない。秀司はとても、優しい人だから。
考えなしの行動を悔やみ始めて、ふと陽気な声が頭の中に響いた。
――男なんて抱きついときゃおちる。
ああ、あの戯言の所為だ。そう思ったら、少し気分が軽くなった。
駄目だった時は責任をとってもらおう。そうだそうだと内側からも声が起こって、可笑しくなる。
訝しんだ様子で再度秀司が智姫の名を呼ぶ。
うん、と返し、抱き締める腕に力を込めた。



