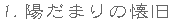
-3-
松葉杖、で連想される単語がぽんと浮かんだ。すっかり忘れていたけれど、鞄の中には携帯用のアンダーアーム型クラッチを常備していた。松葉杖ほど存在感はなく――使用していればそれなりに注目は浴びるけれど――歩行の補助を請け負ってくれる便利なアイテム。
緩やかな坂道だからとなめて掛かっていたのは否定しない。気合いをもってすればこんな道くらいに負けてなるものか、と意地を張ったことも否定しない。
坂道に差し掛かった時点でそれを使用していれば、負担は軽減されたのに。と悔やむも、あとの祭。
なに?という含みのある視線を投げ掛けられたが、気づかないふりをして鞄をまさぐった。
どちらかといえば几帳面な性格が功を奏し、鞄の中は整頓されている。すぐさま取り出せた。しばらく座っていたおかげで、気分もだいぶ落ち着いてきている。
「これ、あるから大丈夫、です。あたしはもう少し休んだら行きますから。ありがとうございました」
ちなみにリハビリを受けている者ではないです、と付け加えようと思って、やめた。律儀に勘違いを訂正する必要はない。
見た所、健常者そのものだった。隣町の高校の名前が入ったジャージ上下に大きなスポーツバックを肩から提げている。運動系の部活でもしているのだろう。日焼けしているのでおそらく外の部活だと推察する。
健康優良児と表現しても誰も否定しなさそうな、締まった体躯をしていた。
リハビリを必要としている人ではないと判断する。第一、リハビリを要する者がこんな坂道を歩こうとはしない筈だ。大方、一時入所している誰かの見舞いといったところだろう。
となれば、今後センター内で会う機会などそう無いだろうし、誤解されていたとしても何ら問題があるとは思えなかった。
今度は、少しくらいはマシな笑顔で言えた自信はあった。
心配してくれる人を相手に、安心をあげられるのは、こちらが笑顔を作れるということだ。と華保は信じていた。
なのに、
「荷物持ちくらいはできるって。遠慮無用」
にべなく却下される。
これは彼の性分なのだろうか。華保がどう返そうとも、無しの礫状態。こうなれば強硬手段に出るしかないか、と気を引き締める。
幸い、膝の痛みは消えていた。
このままでは、申し訳ないやら居た堪れないやらで対面しているのが辛い。
「それがないと、歩行厳しいのか…?」
遠慮ない問い掛けの中に、僅かな違和感を覚える。
今までにもクラッチ使用時に同情的な言葉を掛けられたことは何度もあった。初めの頃こそ、そんな好意にさえ心は波立っていたけれど、それもいつしか麻痺していった。
今以上の好転は望めない現実に期待を馳せても仕方がないのだと、ようやと最近になって区切りがつけられるようになっていた。
直球の質問に胸を痛めることなど、無くなっていた。だから気分を害することはなく、違和感は単なる思い過ごしだと結論づける。
そもそもこの人は、自分をリハビリ患者だと思い込んでいるのだ。質問の仕方が若干変に感じられたからといって、勘繰る方がおかしいというもので。
リハビリ患者に補助器具が必要なのは当たり前のことで、単純に華保の年齢――おそらくは自分と大差ない年齢なのに、と不憫に思っているだけなのだろう。と、更なる結論をつけた。
「普段はこれがなくても歩けます。ちょっと坂道なめてました」
乾いた笑いを向け、おどけてみせる。だいぶ余裕が出てきた。
これならいける、と地面に手をつき、押した。いまだ頭の中が多少ぐらぐらしているのには目をつぶる。
この後に向けられるだろう同情の視線だけは、回避したかった。
一人でも大丈夫なのだと、自分はもう、一人でやっていけるのだと、示したかった。目の前の人に。
――何より、自分自身に。
華保がとろうとしていた行動の先読みに一瞬遅れをとった彼は、焦燥を滲ませた。
「ばっ…急に立ち上がんなっ…!」
華保に続き慌てて立ち上がるのが見えていた。ひと足先に立ち上がっていた華保は、自分がちゃんと立ち上がり、クラッチを支えに自身の身体を立て直していたと、認識していた。
それは大きな認識違いで。
にっこりと笑ったつもりだった。しっかりと自分の脚で立っているつもりだった。頭がぐらぐらしているのはなくなったものだと、思い込もうとしていた。
現実は、立った瞬間ぐらりと身体は傾ぎ、中途半端な笑顔が浮かんだ直後、景色の一切が暗転した。
暗闇で体感していたのは、たゆたうぬくもり。揺れる心地よさだった。



