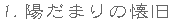
-4-
無音の暗闇に、薄っすらと光が差し込んだ。遠くから、人の声が聞こえる。さざめくような声の遣り取りが耳に心地よい雑音として届く。人の気配が傍にあることが、不明瞭な安心感をもたらしていた。
深く深く沈んでいた己の意識が、ゆっくりと浮上していく。
目覚まし時計に強制的に引っ張り上げられるのとは違う、穏やかな覚醒。まだこの暗闇に残っていたい気もしていたけれど、華保の意識はそれを許さないらしい。
徐々に耳に届く声が鮮明になっていく。名残惜しさを振り切って、ぎこちなく目蓋を持ち上げた。
天井が見えた。真上にある蛍光灯はついていない。視界の端に光源が感じられて、そちらへ顔を動かす。人の頭があって、その向こう側の灯りが点いていた。華保が目覚めた時、眩しくないようにしているのだな、と判る。
華保の傍らに座る人物の顔は向こう側を向いていて、後頭部にかろうじて横顔の一部が見えるくらいの角度だった。誰かと話してる、とぼんやり眺めていると、立っていたもう一人が華保の目覚めに気づいた。
「華保ちゃん、よかったー。吐き気とかない?」
見知った顔が、安堵と笑顔を綯い交ぜにして寄ってくる。そこで自分は長椅子に寝かされていたのだと知る。身体を動かそうとしたら、骨がぎしりと音を立てた。
「起き上がらなくていいわ。しばらくこのままで」
おでこにあてられた手が優しく浮きかけていた頭を戻す。
「都さん…。あたし…?」
なんでここにいるのでしょう?
華保が寝かされている長椅子は職員専用ロッカー室に置かれているものだった。正式な職員ではないけれど、華保もセンターへくる度に使用させてもらっていた場所だ。
どうやって辿り着いたのか、記憶が全くない。よもやワープしたわけでもあるまいし。
「気分はどうだ?」
都越しに、さっきまで傍らに座っていた人物が問い掛けてくる。
「あっ!」
驚きのあまり飛び起きそうになって、今度は肩をやんわりと押さえ込まれた。
おでこにあてられていた濡れタオルがずり落ちる。お構いなしに視線は釘付け状態。
見つめられた方はといえば、呆れた視線を向けていて、手にしていた方のタオルを華保のおでこに乗せ、落ちた方を引き上げる。
「大人しくしてろって」
ずっと、傍にいてくれたのだろうか。だとすれば、相当な迷惑をかけたのだろうと、容易に想像がついた。
「もしかして、あたし、倒れ…ちゃったんでしょうか?」
おそるおそる訊ねる。答えを聞きたくないような、聞かなければならないような。
「…その通り」
溜息混じりに言われ、肩身が狭くなる。



