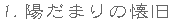
-5-
「尚。冷たいものでも買ってきて」都は諌める口調で振り仰ぎ、背後に立つ少年に言う。続けて華保に向き直る時には、いつもの柔和な雰囲気を持つ都が戻っていた。
「華保ちゃん、リクエストある?」
「あ、いえ。いいです。あのっ…」
「いーのよ。じゃー適当に買ってきてくれる?」
有無を言わさず紙幣を握らせられた少年は「了解」と呟き出口へと向かう。ドアを開けたところで「姉貴は?」と振り返った。
「私は要らないわ。仕事戻るから」
ぱたん、と扉が閉まり、ドアが開いていた間だけあった喧騒が再び遠いものになる。
「弟さん、ですか?」
都同様ドアの方を見遣っていた華保はぽつりと質問する。似ているといえば似ている気もした。
都と知り合って数年が経つが、そういえば家族の話はしたことがないな、と思い返す。
「十歳違いの生意気な弟よ」
色々思うところはあるのだろうか、辟易したように話すくせに、どこか嬉しそうでもあった。仲が良いのかな、と想像する。
同時に、都のような姉がいる彼が羨ましい、と心底思ってしまう。
ぎりぎりの境界線で、華保を歩けるまでに回復させてくれたのは、都だった。
感謝しても、し足りない恩人だ。本人に言えば本気で照れて嫌がられるので、改まって言えたのは一度きりだった。それ以降は緘口令が敷かれた。
幾人も救ってきた人だった。その度に向けられる感謝を、都は言葉にされずとも感じ取っているのかもしれない。
「あたし一人っ子だから、羨ましいです。十個違いってことは、あたしと同い歳ですか?」
あんな風に道端で蹲っていた華保を発見しても動じた素振はなく、よほど場慣れしているのか、そうでなければ年上なのだと思っていた。だから丁寧語を心がけていたのだ。
同じ高校生だと判明した後も、絶対自分よりは上の三年生だと思っていた。
「そうなるわね。身体ばっかり大きくなって、立ってるとすっかり見下ろされちゃうのよね」
いかにも気に喰わない、という口調をわざとらしく言うのが可笑しかった。いつだってこうやって、都は人を和ませる。
リハビリセンターの職員という職種は彼女の天職だ、と華保は思っている。目指すは、都のような理学療法士。
自分と同じ、後悔の路を辿る人を作りたくない。それがきっかけだった。華保の、大切な目標。
「つかぬこと、お聞きしたいのですが…」
意識の暗転した時が倒れた時なのだというのは明白だ。尚と呼ばれた彼は近くにいて、置き去りにしてきたとは到底思えない。センターに連絡をして、都に車でも出してもらったのかもしれない。
一人でも立っていられるようになりたい。そう決意したばかりだというのに…。
悔しさが湧き起こる。
寝そべったまま話をするのはどうも気が引け、慎重な速度で上半身を起こした。
「訊きたいこと?…ここへ着いた経緯、とか?」
「鋭い、ですね」
苦笑を洩らすしかない。
都は、ほとんどの確率で華保の言いたいことを当ててしまう。超能力者かと、一時期は本気で疑った。ある時冗談めかして言ったら、職業病ね、なんて笑っていたけれど。
それだけ周囲にアンテナを張り、その人自身をみているということなのだ。と今では勝手に結論を出している。
自分を判ってくれる存在が一人でもいるというのは、本当に心強いことだった。どれだけ都に救われたか、計り知れない。
「仕事忙しいのに、手間かけさせちゃってすみません」
ぺこりと頭を下げる。
初日から迷惑しか掛けてないなんて、先行き不安だ。
「気にすることないわよ?ここに運び込まれてからそんなに時間経ってないもの。私は合間に待ってただけだしね。仕事の妨げになるほどじゃないわ」
たっぷり眠りこけていたわけじゃなかったことに胸を撫で下ろす。が、遅れて都の言葉を吟味すれば、とんでもない思考が浮んできた。まさか、と即座に否定したいのに、都はあっさりと続けてしまった。
「尚がここまで運んでくれたのよ。こう、抱っこして」と両腕をくの字に曲げ抱き上げる格好を真似る。
軽やかにあっけらかんと都は言う。対して華保は言葉を失い茫然と都を見つめた。
ふぇ!?などと空気が漏れたような音を発して慌てて飲み込む。顔で熱が弾けた。
「お姫様抱っこってやつよねー。あいつもたまには役に立つものね」
都はからかう気たっぷりだ。
「み、都さんっ!」



