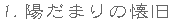
-7-
ぽんと返された意味が全く判らなかった。間抜けな声を洩らし、間抜け面を晒して、相手の顔に答えを捜すべく、凝視した。それこそ穴があくほどに。「やっぱりな…。覚えてないか」
残念とも諦めとも孕んだ語調で、落胆が窺えた。
「え?……えっ!?」
いつ会った人だろうかと、慌てて記憶を検索し出す。迷惑かけた上に面識があったことを忘れていたなど、失礼極まりない。
焦れば焦るほどにこんがらがって巧く探れない。
「あー…、いーよ。無理せんで」
見るに見かねた、といった様子でパニクる華保を止めにかかる。怒っている、というよりは、華保の慌てっぷりに興を見つけた顔つきだった。
「会ってた、ってゆったって、もう何年も前の話。でもって、数回会った程度だから」
判らなくても当然だよ、と付け加えるが、それならば双方条件は同じではないか、と思う。自分だけが覚えていないのは、何ともばつが悪い。
そして何だか、悔しい。変なところで負けず嫌いな気性がむくむくと目を覚ます。
ネタばらししようというのが雰囲気で判ったので、慌てて遮った。
「待って、待って。今思い出すからっ」
良尚は一瞬きょとんとして、遠慮なく噴き出した。おなかまで抱えて笑ってる。
「そーゆう意地っぱりなところ、全然変わってねーのな」
むっと唇を引き締めた。ますますムキにならざるを得ない。
しばらくじっと相手の顔を見つめて、見た目から連想するのは諦める。何年も前、がいつを指しているのか判らなく、加えて彼のような容姿であれば記憶に残りそうなものだった。
残されたヒントを拾い上げて、じっくりと向き合ってみる。といっても、ある持ち札は名前くらいなものだったけれど。
彼の本名は「東郷良尚」で、姉である都は彼を「尚」と呼んでいて…。
「尚…?」
呟く音量で声に出してみる。華保が真剣に考え込んでいる様が可笑しいのか、良尚はさきほどからずっと、笑いを低く噛み締めていた。
「東郷…良尚くん。…尚。……あ、」
ぱちんとシャボン玉が弾けるみたいに、記憶が蘇ってきた。取り巻く空気が、一気に過去へと戻りそうになる。
笑顔で溢れていた、あの夏に。
「……尚くん?」
「はい。正解」良尚はにっこり笑う。



