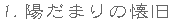
-8-
この場所で、夏休みの数日を、共に過ごした相手だった。「尚くんだっ?」華保の声は裏返り気味になった。
「正解だ」良尚は深く相好を崩した。
「うわ、懐かしい」
「だよな。にしても、全く気づかないんだもんな」
俺は一目で判ったのに、と本当とも嘘ともとれる口振りで付け足す。
「無理だよ。尚くん変わりすぎ」
よくよく見れば、で面影は若干ある気もするが、これで気づけっていうのは酷すぎる。
小学校の夏休み。華保はセンターに勤める母親にくっついて施設に遊びに来ることが多かった。共働きで忙しい両親に構ってもらえない代わりに、センターは華保の遊び場同然で。
夏休みの間を過ごすことになった「尚くん」は、都についてセンターにきていた。同じ年頃でリハビリのない二人が仲良くなるのは、自然の流れみたいなもので。
「あの頃って、両親と離れて暮らしてたんだよね?祖父母の家に住んでるとか、言ってなかった?」
華保の掘り起こす記憶が正しいことが嬉しいのか、良尚は綻ぶ。笑うと、太陽が咲くような明るさがあった。
笑顔、変わってないかも。
記憶の波は少しずつ押し寄せる。
小さな彼は、いつでも楽しそうに笑っていた。都が彼を「尚」と呼ぶから、華保も「尚くん」と呼んだ。フルネームとかプロフィールとか、細かなことには一切頓着しないのが子供の特徴だ。
一緒にいて楽しければ、仲良くできればいい。それだけが一番に大切。
「今は実家で、両親と、あの姉と暮らしてるよ」
あの、を強調して良尚は言う。
姉の顔でいる時の都がどういう人物かは知る由も無いけれど、弟に対してはズバズバいきそうだと想像できて、笑ってしまう。
「俺さ、こう見えても喘息持ちだったんだよね」
何故祖父母の元にいたのかと、気にはなったが訊けずに、他の話題を、と捜していたら拍子抜けするほど簡単に、良尚は答えを綴り出した。
「今は?」
「よくなったよ。小児喘息だったし、今じゃ運動系の部活に入ってるくらい。ガキの頃は空気の悪いとこで生活できなくってさ。田舎に預けられてたってわけ。でも、やっぱお子さんの時は親が恋しいもんなんだな」
子供が親を恋しがるなんていうのは当然の心理なのに、それを素直に口にするのは至極恥ずかしいといった様子で、少し歯切れ悪そうに良尚は言った。
期間限定で実家に戻っていた時に、都にくっついて施設へきていて、出逢った。
「でもやっぱ家にいるとどうにも発作が出がちでさ、強制的にここに連れてこられてたんだよな」
「ここは空気いいもんね」
「おかげでここにいる時だけは発作もなかったな」
「全然知らなかった。元気そのものだったよね」
どちらかといえば、野生児みたいに走り廻っていたよね。とは黙っておく。
やんちゃそのものだったあの「尚くん」が、一目見ただけでは判らないくらいに成長して目の前にいる。不思議な感覚だった。
記憶と合致する箇所を見つける度懐かしさは込み上げるけれど、それ以上に、胸の内側がもそもそと落ち着かない。
「今は、正真正銘元気そのものだ」
「みたいだね。部活はなにやってるの?」
着ているものは、学校指定のジャージではない、と推察する。校名が入ることはまずないからだ。だとすれば、部活帰りに立ち寄った、という解釈が合っている筈だった。
「陸上」
軽やかに紡がれた返答に、鼓動が鈍く鳴った。こんな単語一つに、まだ動揺してしまう自分に、嫌気がする。缶を持つ指先に力がこもった。



