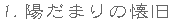
-11-
右も左も判らない状態のまま、時間は着々と経過していく。始まったばかりで、しかも知識は皆無の素人が、現場にいたところで何ができるわけはなく。壁と友達よろしく、邪魔にならないよう端っこにいるのが当座のできることだった。
ただ、現場の空気を感じられただけでも、貴重な体験で。
合間の休憩で壁際にいる華保のところまでやって来た都は「あまり構ってあげられなくてごめんね」と謝罪を口にした。
とんでもない、充分です。と慌てると、ほんの少し安心した顔つきになる。
一対一が基本なのだが、都は立場上、他の職員からアドバイスを求められたり周囲に気を遣ったりで、華保にまで気が廻らないのは当然だった。
理学療法室に踏み入れてからの時間、声には出さずにいたが感嘆するばかりだった。
「……やっぱり、すごいです」
休憩を早めに切り上げてリハビリに戻る倖汰を、都と並んで眺めていた華保は呟いた。
「うん?」
首を傾げたのが、そちらを見なくても気配で判った。今度ははっきりと「都さんは、すごいです」と明言する。
「あたし、母と同じくらい、都さんを尊敬してます」
事も無げに宣言した。
真剣に取り組んでいた倖汰へと、恥ずかしそうに視線を動かしていた都は、巧くできたことで顔を輝かせ自分の方を向いた倖汰に、笑みで応える。
「倖汰くん、上出来!」
照れ隠しに他で誤魔化そうとしているのが明確で、笑いを堪える。
都の内情など離れている所にいる倖汰には判らず、褒められたことを純粋に喜んでいた。
こんな一言が、あの子にとってどんなに励みになっているのかを、華保は実体験をもって知っていた。
◇◇◇
華保がセンターに通うようになって、一ヶ月が経過していた。あっという間の一ヶ月。
学校に通いながらでは毎日というのは難しかったけれど、できる範囲で足を運び、雑務をこなす日々だった。
そんな生活がきつくない、といえば嘘になる。きついだけなのか、と問われれば、答えはノーだ。
志すものがあるから挫けてなんかいられない、といえば聞こえはいいが、センターに行く楽しみが増えたのがあって、そうそう苦難なだけでは無くなった。
誰かに話せば不純だと言われても否定はできないので黙ってはいるが、勘のいい都にはばれてるらしい節はある。
この一ヶ月、もっぱら雑用係としてセンター内を動き廻っていたおかげか、あちこちに知り合いができた。こういった業種に就くような人達は、往々にして人当たりのいい者が多いらしい。馴染むのにそう時間は掛からなかった。
滑り出し順調と綻んでいた中に、いい方向で、華保の予想を裏切ったことがあった。
思いの外、良尚と会う機会があったのだ。数年振りの再会後も、良尚はセンターを訪れている。しかも結構まめに。
人遣いが荒いと姉に辟易していたのに、何だかんだで依頼を引き受けているのだから、根はやっぱり優しいのだろう。本人に言えば怒られそうなので口にはしていないが、心の中では都に拍手喝采を送っていた。
初めて会った時から華保の中で、かすかな信号はあった。優しくて、とても小さな信号。
だけど、確かな。
逢う度に、言葉を交わす度に、緩やかに強く、大きく成長する想い。
大切に、育てたいと思っていた。



