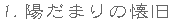
-12-
朝から灰色一色の空模様。午後に入る頃にはポツリポツリと天から雫が落ちてきていた。学校が休みの週末、華保はセンターにいた。
蛍光灯が灯っていても薄っすらと室内は暗い。湿った空気が肌に寄り添っている。
天候が優れないと、どことなく全体的に元気が削がれているように見えるのは、単なる気のせいかもしれない。あちらこちらで作業をしながら、そんなことを華保はぼんやりと思っていた。
青空より、まし。
本音とも虚勢とも覚束無いことを無意識の内に自分に言い聞かせていて、自嘲気味に笑音を漏した。
昔の古傷が雨の日に疼く人がいるという話は聞いたことがある。華保の場合、晴天の『青』がまさにそれだった。
左脚を駄目にしたのは、他ならぬ自身の弱き心だったというのに。
逆恨みでしかないそれを自覚させられる度、己を嘲笑う。
あの日の空は、突き抜けるような碧空。記憶にきつく刻まれた、青。
自分の足が地を離れ、ほんの数秒重力に逆らい、独り占めした空。あの浮遊感を、青を、確かに好きだった。
――華保が失った、空。
穿たれた傷痕は、今なお、華保を苦しめていた。
けれど。
それを周囲に悟られてはいけない。そう、堅く誓いを立てた。こんな弱さなど、曝け出したくなかった。
強くならなければと、願う。
時刻は夕刻に差し掛かり、夕飯の準備を手伝うべく、食堂のテーブルを拭いて廻っている時だった。
本日の日程を終了させた都が隠しきれない疲労を滲ませながら入ってきた。途次にいた華保に向けた笑顔にも、疲れが見える。
「お疲れさまです」
都は歩みを止めず、奥にある調理場へ一直線。足を動かしながら顔だけを華保に向けた。
「お疲れさまぁ。華保ちゃん、夕飯一緒できるの?」
「はい。今日は母と帰りますので」
華保の母親はまだ臨床中だ。
「今日って、お昼で帰るって言ってなかった?」
問い掛けておきながら都はその返答を聞かずに調理場を覗き込み、「いい匂いねー」などと嬉しそうにしながら献立を聞いている。
しばらくすると満足したのか、華保の近くまで戻ってきた。
「そのつもりでいたんですけど。雨降り出したし、他にやりたいことできちゃってそのままズルズル残っちゃいまして」
「こちらとしては助かるけど、大体、今日は担当日以外だったんだから、休んでも良かったのに」
「優先したいことが他にできたら、そうします」
家にいてもすることがないとは言わないけれど、倖汰の治療がもうすぐ終わる。できる限り顔を合わせていたかった。
「優先、ねぇ。例えば…彼氏、とか。――いないの?」
一瞬は鼓動も波立ったけれど、からかいを帯びていたので押し込めた。
「彼氏いたら、もっとここには来ていません」
「それも、そうね」
揶揄を追撃する気力がないのか、都は大人しく引き下がった。ほ、と息を吐こうと油断したのが、悪かった。
「尚ね、」
「へっ?」
唐突に名前を出されて、今度こそ心臓が跳ねたのが表面化してしまった。都はしてやったり顔だ。やられた。
「今日くるって」
「…あ、そう…ですか」
悔しいが、にわかに騒ぎ出した鼓動を平常にすることができない。本当に悔しいのだけど。
手伝うわ、と都も布巾を手にし、近くのテーブルを拭き始める。
「尚ね、最近明るくなったの」
これまた唐突な話題だな、と思いつつも、先ほどよりも落ち着いて耳を傾けることができた。
調理室は間近に迫った夕餉の時刻に急かされていて、最後の仕上げにおおわらわだった。こちら側の会話には気にも留めていない。
華保はからかい易いオーラでも醸し出しているのか、センターの職員達に揶揄されがちだった。好意的なものは感じられるので本気で嫌がってはいないのだが。
都が最近ネタにしがちな話題は、特に調理室のおばさま年代の面々には喰い付きどころで、できれば聞かれたくなかった。忙しいのは幸いだ。
「もともと明るいんじゃないんですか?よく笑ってますし」
「…以前はね。今は戻りつつある、と言った方が正解なのかな」
独り言のようで、問い掛ける響きがあった。
都の言う「以前」は、華保の知るそれと同位ではない。ということだけは明確だった。
目の前にある表情から、問うていいものか躊躇う。
「ここ数年は違ってたの。ある事がきっかけだったんだけど」
聞いてくれる相手を探していた風でもあって、そうじゃないようにも見えた。都の中に迷いがあるのだけは確かだ。『ある事』を勝手に話せないだろうし、だとすれば訊ねても困らせるだけ。
「喘息の方は良くなったんでしょうか?本人はそう言ってましたけど。小さい頃は家にいるだけでも発作出てたって…」
詳しいことは知らないけれど、結構重症に入っていたのではないかと想像する。
「小児喘息は成長すれば治る方が多いの。今ではすっかり、見たまんま元気ね」
話題が逸れたことに安堵したのが、判った。突っ込まなくて良かったと、華保も胸を撫で下ろす。
いずれ、話したい時がくれば、本人の口から聞けるかもしれない。
人の過去を穿り返すのがどれだけの苦痛を強いるかを、知っている。だからそれを、他の誰かに向けるのはしたくなかった。
好奇心を咲かせて押し付けるのが、一番たちが悪い。
思い出すと、今でも眉をひそめたくなる。
「人遣い荒いって、ぼやいてましたよ」
「あら。そんな風に言ってたの。へぇ」都は思案顔になる。
その表情の語るところの向け先が自分にないと判っていながらも、まずいことを言ってしまったかと悟る。が、もう遅い。
嘘は言ってないから、よしとする。ことにした。
「最近はよく、華保ちゃんの話題が出るわね」
それならば代わりに、といった感じで都は言う。悪戯っ子な笑みは、子供みたいで可愛い。
「どんな悪口言われちゃってるんですか?」
悪口、は少し誇張しているが、何かの度にからかわれているのは事実だった。元を辿れば、華保のドジが原因なのだけれど。
人に迷惑をかける程のドジはやらかしてはいないが、自分の身に降り掛かる程度の小さなものをちょこちょこやらかす。その度にからかってくるのだ。
傍にいられるのは嫌ではないが、じっと見られているのは何とも落ち着かない。というか、緊張してしまう。故に、ドジも起きがちで。
判っていて見つめている節は否めない。
都さんと一緒で人をからかって楽しんでますよ、血は争えないですね。とは口が裂けても言えない。
「そんなわけないじゃない」
しらっと言い放つ。その笑顔で後に続く言葉を聞くのが怖い。
聞きたいような、耳を塞ぎたいような。
華保の心情にはお構いなしに、都は続けた。
「話易いんですって。女の子の話題なんて持ち出したこと無かったから、ちょっと驚いてるのよね」
と言ってても、ちっとも驚いている様子はない。
ここで変に照れたり動揺してしまったら相手の思う壺だ、と判っていても、平静でいられるわけはなく。
胸の奥からじわじわと湧き上がる悦びを、奥歯を噛み締め何とか押えた。
タイミングよく、出来上がった調理品並べの指示が調理場から飛んできて、助け舟にすぐさま喰い付く。小走りになる華保の後に、都は「残念」と本当に残念そうに呟いて続いた。



