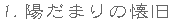
-13-
粗方の準備が整い、ちらほら人が集まり出す頃になっても、どことなく心がささめいていた。落ち着かない。そんな心地でいたものだから、ポケットに入れていた携帯電話が震えたことで、びくりと肩を揺らしてしまった。誰にも見咎められなかったことを素早く確認し、廊下に出る。
メールの着信だった。送信者は良尚。
名前が目に入った瞬間、とくんと鼓動が優しく波打った。さきほどの都の言葉までも思い出してしまい、口元が緩んでしまう。
誰に見られたわけでもないのに恥ずかしく、俯き加減でメールを開いた。
『タオル借りれる?』
素っ気無い一文が表示される。文面を確認した時には歩き出していた。リネン室に立ち寄り、清潔な香りのするタオルを手に取る。
『到着してるの?玄関?』と返信を打つ。
身体はすでにそちらへ向かっていて、エントランスホールが見えてきたところで、着信音が聞こえてきた。良尚のものだ。自分の読みが当たっていたことに満足する。
携帯電話へと視線を落としていた良尚の名を呼ぶ。顔を上げた彼の姿に驚き、固まった。
予想していたよりも遥にずぶ濡れで、おまけに泥まで跳ねていた。しかも結構な広範囲で。
そこでようやく、空模様を改めた。いつの間にやら土砂降りだ。叩きつけるほどの雨が地面で跳ね返っている。激しい雨音に気づかないほど他に気を取られていたのかと、己に呆れてしまう。
良尚の制服を見事なまでの泥模様にしているのは雨だけが原因ではないのでは、と思っていると、疲れた様子で良尚が答えを紡いだ。
「さっきそこで車にぶっかけられてドロドロになった。雨で綺麗になるかなぁ、なんてのは都合よすぎたな」
いつもは太陽みたいに笑う良尚もさすがに参っているらしい。笑顔に活力が無い。
華保としても苦笑いを返すしかなく、見ているこっちが寒くなってくる。
「これ、タオル…」
こんなことならバスタオルにするべきだった。フェイスタオルサイズでは焼け石に水だ。
「ってか、大きいの取ってくるよ。てか、上がって!あったかい飲み物用意してくる。あー、それより先にシャワーだ」
「華保、落ち着けって」
握り締めていたタオルに手を伸ばし、持っていく。「サンキューな」
僅かに触れた良尚の指先は氷のように冷え切っていた。想定通りにタオルは瞬く間に水分たっぷりとなる。
「うわ。泥だらけになった。ごめん」
自身で思っていたよりもひどい状態だったと驚いている。
「とにかく上がって。風邪ひいちゃう。シャワー室行ってて。用意してすぐ行くから。制服も乾かさないとね」
矢継ぎ早に指示を飛ばし、踵を返して駆け出そうとして、どん、と何かが体当たりしてきた。
「倖汰くんっ?」
「急に振り向かないでよ!華保ちゃんっ」
抱きつく格好と受け止める格好で互いに顔を合わせる。リハビリ完了間近の腕と激突しなかったことに安堵する。
「ごめん、ごめん。急いでどーしたの?」華保は受け止めたまま問い掛ける。
「つか、廊下走った倖汰が悪い」どことなく良尚は不機嫌そうに言う。
「ママ姉!」謝ろうと動いていた筈の倖汰の唇は、違う音を発した。
きょとん、としたのはその場にいた良尚だけで。
華保が合点顔で出入り口を見遣ると、傘を畳んでいる人影を発見した。
「ママ?姉?お姉さん?まさか…母親、ってことはない、よな?」
自分の認識能力を疑うような良尚の口振りが可笑しい。
「伊吹さん、お迎えですか?」
声を掛けられた蕪矢伊吹は、華保と倖汰を見つけ、緩やかに笑顔を向けてくる。
「すごい雨だよね。傘が役に立たなかったぁ」
うんざりした表情で近づいてきて、良尚の姿に驚いている。「あたしよりひどい人がいた」
「いきなりの本降りで、傘なかったんで…」応える良尚は胡乱げだ。
近くで見ても、せいぜい多く見積もっても自分達の二、三個上、といったところだ。と思っているのだろう。
「ほんと、急にきましたよね」伊吹は良尚の様子には気にも留めることなく、大変ですね、という視線を向け、それから倖汰を見る。「いつまでくっついてんの?倖汰」
言われて、パッと倖汰は離れた。顔が少し赤くなっている。
人懐っこい倖汰のこんな行動は普段通りとも言えるので華保は気にしていなかったが、どうやら伊吹の前では見せていないらしい。
「良尚。こちらは蕪矢伊吹さん。倖汰くんの母親代わりなの」
ママ姉というのは倖汰専占の愛称みたいなもの、と説明する。
倖汰の母親は伊吹の実の姉で、昏睡状態のまま年数が経っている。伊吹は母親代わりであり姉代わり。なのでママ姉、と呼んでいる。
一番初めにこの呼び方を聞いた時は、華保も今の良尚と同様の反応をした。
「タクシー呼びましょうか。その前に、伊吹さんにもタオル持ってきますね」



