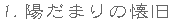
-14-
きちんと整理整頓されたロッカー室で、窓際に椅子を引き寄せ、華保は外を眺めていた。窓を叩く雨音は激しいものではあったけれど、遠い世界の音に感じる。それよりもうるさいのは、自分の鼓動。これまでだって二人きりになることは幾度もあったくせに。
たぶん都からあんな話を聞いた後だからだ。
暖房を点けたばかりで、室内温度は充分なほど温まってはいない。シャワー室からきたばかりの良尚が、かえって風邪をひく事態にならないだろうかと心配になる。
華保でさえ、肌寒さを感じるくらいだ。
「制服、乾くまで時間かかりそう」
暖房機器の近くに良尚が座る用に椅子を用意していたのだけど、ひょいと持ち上げ近づいてきたと思ったら、華保の隣に座った。
意識しすぎている自分を諌めると同時に、意識されなさすぎな相手の態度に、ほんの少し、物悲しさを感じてしまった。
「なにからなにまで悪いな」
洗ったばかりの髪を無頓着な所作で拭きながら、華保と同じく視線を外に置く。制服が乾くまでの間、鞄の中で無事難を逃れていた部活ジャージを穿いていた。Tシャツから伸びる腕は日焼けして、細いのに引き締まっていて逞しさもある。バランスよく鍛えているのだと感心する。
陸上選手の身体つきだった。そう思って、陸上という単語に、心が揺れた。
己の思考なのに、動揺する。手の中のマグカップに満たされている褐色の液体が、手の震えに呼応して波紋を作った。動揺している自分に、落ち込む。
見られたわけでもないのに、誤魔化そうと、唇を引き結んだ。
今だ引き摺っているのは、弱さがそうさせる。これは己の内への闘いであって、他を巻き込む必要はないのだ。一人でどうにかするしかない。
こんな時こそしっかりしなくては。そうでなければ、いつまで経っても、真の強さは手に入れられない。強くなれなければ、都のように、誰も救うことはできない。
笑みを刻みつけ「どういたしまして」と返した。
不意に目線がぶつかると騒ぎ立てる鼓動が表面化しそうで、顔で熱が弾けそうになる。変に思われるのだけは勘弁だ。
「あ、あのさ、紅茶でいいかな。用意してあるんだ」
伊吹と倖汰がタクシーを待つ間、ミーティングルームで待機してもらったのだが、その間に用意した紅茶と同じセットを、もう一組用意していた。
シャワー後に紅茶というのもどうかと迷ったりもしたが、なかなか上がらない室温に、結果オーライということにしておく。
「サンキュー」
「待ってて」
緩やかな笑みを正面きって受け止められる余裕はなく。急激に立ち上がったことで少々派手に音が立ってしまったが、気にしないことにしてテーブルへと急ぐ。見られているかも、なんて背中を向けているから単なる自意識過剰なだけなのかもしれないのに、落ち着かない。
良尚は、落ち着き払った態度でいることが、時々ある。それは数年振りの再会の時も然り。普段は自分と同い歳な認識を与えるくせに、だからこそ『その時々』は、ずるい。
湯気を立ち昇らせるマグカップを手渡し、座っていた椅子に戻った。離れて座ろうかとも過ぎったけれど、あまりにも不自然なので止めておいた。嫌っているなんて誤解をされても困る。
一人あたふたしているのが、悔しい。
「雨、激しーなぁ」暢気に、下手をすれば感嘆の響きすら伴って、良尚は言う。「せっかく乾かしてもらっても、元の木阿弥になりそうだ」
「ほんとだね。今日は都さんと帰ったらいいんじゃない?」
職員の大半は車通勤だ。空気がいい場所、というのは往々にして、交通機関の不便な場所にありがちだ。
「姉貴は泊まり勤務じゃなかった?」
「…あ、そうか。だね」
思考回路がちゃんと記憶を繋ぎ止めてくれていない。舌打ちしたい気分だった。
「じゃあ、母さんに聞いてみる。送ってってくれるよ」
「いーって、俺のことは。それよりさ、この前の地区大会で自己新記録出したんだ」
嬉々として、報告をくれる。
華保が高飛びに詳しいことを知って、それ以来なにかある度に話題に上がる。本人が言うように、本当に良尚は高飛びが大好きで、その気持ちは、華保も共鳴できる部分だった。
悦びを素直に話してくれる相手として選んでくれたことは心底嬉しい。共通の話題で盛り上がれるのは楽しい。
だからこそ、過去を抱えた弱い自分を払拭したいと願う気持ちは、以前よりも更に増している。
「またなんだ?すごい。向かうところ敵無し、な感じ?」
「それは大袈裟。まだまだすげー奴はいっぱいいる」
悔しがるというよりは、前向きな生き生きとした表情だ。つられて、明るくなれる気がした。
「そっか。目標は高く?」
「勿論」
良尚は、高校二年生ながらに大学からスカウトがきているらしい。推薦枠の確保がされているとかいないとか。
この話は本人からではなく都から聞いた。都に教えられて本人に訊ねたこともあったが颯爽とはぐらかされて以降、話題にはしていない。どうやら照れ臭いらしい。
「始めたきっかけは?」
そういえば聞いてなかったな、と思い返す。
ここまで夢中になれる理由は、華保自身も知っている。共感できるからこそ、良尚も華保には話をしてくれる。
「あれ。話してなかったっけ?中学ん時さ、友達が出る大会を見に行ったんだ。そん時は全く興味なくて、半ば強引に連れてかれたんだけど」
そう言って、良尚は懐かしむように目を細めた。
たまたま見に行った大会で、たまたま見つけたハイジャン選手。年齢の割には小さな身長の少女。
はじめ見た時は、身長がなくても選抜選手になれるんだな、という程度の認識しかなく、意識は友人の応援に向かっていた。
その少女が決勝戦まで残っていることに気づいた時から、目が離せなくなった。
優勝争いしか注目しなかったことを、遅まきながら後悔したという。
跳ぶ姿は、鮮烈に、良尚の目に焼き付いた。
碧空に溶け込むかと錯覚した。鮮やかに、力強く、しなやかに、大きく広げる翼が見えた。気がした。
翌日には、躊躇うことなく入部届けを提出したという。
あの選手のように跳んでみたい。近づきたい。何よりも、同じ世界を、見てみたい。
中学の陸上界では知らぬ者がいないほど、その少女は有名だった。
自分が記録を残せたら、少女に話し掛けようと決めていた。大会に参加できるほどに実力をつけた後でも、名を挙げるまでは、追いつけるまでは、遠くから見守るだけと決めた。
結局、少女と間近で対面する日は、訪れなかった。
中学で最後の、その年で一番大きな大会で、少女は担架に乗せられ、フィールドから去っていった。高校へ上がった後も、一度とて姿を見ることはなくなった。
「自分のことのように、って言ったら傲慢かもしれないけど、ショックだったんだ。すげーショックだったし、当時の彼女の周りで騒ぎ立てていた奴らに、本気で腹が立った」
良尚は、遺憾そうに唇を噛む。
今だ、悔しさが拭いきれないかのように。



