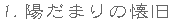
-15-
華保の脳裏に蘇るのは、雑誌の見開きだった。白黒写真に目隠しの補正をされた一人の少女。溢れ出す感情を必死に喉で押さえ込んでいる口元は強く結ばれていた。殴り書きされたような文字形状で書かれた見出しは、当事者への配慮の欠片もない一文。
一過性のものに過ぎないその騒ぎは、人の心の傷を抉るだけ抉って、あっさりと次の標的へと移っていった。残されたのは、痛みだけ。
跳べなくなる、ということが、自分にとってどれだけ大きな損失だったかを、失って初めて、思い知らされた。
自分は跳んでさえいられればよかった。地を離れる刹那の時間が、大好きだった。記録を残すだとか上位を目指すだとか、自分には無関係だと、思っていた。
そんな意識でハイジャンをやっていた筈なのに、いつの間にか周囲の期待を無意識のうちに意識させられていた。重圧は確かに、当時の華保に圧し掛かっていて。
それに応えようとした自分がいたのだと思う。過去のものとなった今だから、気づいたこと。
痛みをおして練習を続けていたのは自分の意思だった。例え言える雰囲気じゃなかったとしても、言うべきだったのだ。でも華保はそれをしなかった。膝が訴えるシグナルを無視し続けて、練習に明け暮れた。靭帯損傷だった。そして、あの大会で踏み切った時、半月版損傷も併発。
自業自得なくせに、自暴自棄になった。挙句、真面目に治療やリハビリに取り組むことを拒絶し、跳べない脚となった。
闇の泥濘から救い出してくれた人達の手は、今でも忘れていない。
歩けるようになっただけでも感謝しなくてはいけない。たとえ人目を引くほどの形であったとしても。
けれど、どうしても考えてしまう。
もう少し早く治療を受けていたら、もう少し早くリハビリを受けていたら、あの時逃げていなければ、今頃はきっと…。
今でも跳びたい。
正直な気持ちが、後悔で埋める。跳びたい、だけど、二度と跳べない。
呼吸が苦しく、息を止めていたことを知る。マグカップが小さく震えていた。
この場から、良尚の視界から、逃げ出したい衝動を必死に消そうとした。
良尚がハイジャンを始めるきっかけを作ったのは、自分だった。その事実は、隠さないといけないと、思った。
跳べないどころか、こんなにも弱い人間になっていたのかと、幻滅されるのが怖かった。
「…ごめん……」
良尚の声が、ぽつりと呟く。その言葉の意味さえ、華保には理解できなかった。聞き返すこともできず、ただ見つめる。
「ごめん、華保。今はもう、跳べないんだよな」
「――知ってた、の?」
華保がその選手だということを。
「左脚に、気づかない訳がない」
非が自分にあるかのように、苦く言う。
喉の最奥が詰まって、声が出せなかった。返せる言葉も、出てこない。
「あれ以降、華保はフィールドに還ってくることはなくて、かといって、逢いに行けるわけもなくてさ。…ずっと引っ掛かってたんだ。後悔した」
「後悔…?」
「記録作ってから、とかさ、つまんない我なんて張ってないで、話し掛ければ良かったって。そしたら、もしかしたら、……俺なんかでも少しくらいは支えになれたかもしれないのにって。ひどい驕りだけど…」
「どうして…そこまで?」
大切に想ってくれたのだろう。単なるきっかけにしかすぎなかった選手のことを。
「俺にとって大事なもんを、教えてくれたから。それに、華保は大事な、幼馴染みだ」
「ずっと、知ってて?」
「男のプライドだの、意地だの、無視すればよかったんだ」
それこそが最大の過失であるかのような口振りだった。「黙ってて、ごめん…」
首を横に振るのが精一杯だった。人の想いがあまりにもあたたかすぎて、目の奥がじんとする。
「華保。俺な、憧れてハイジャン始めた」
「…うん」
ひとつひとつ、ゆっくりと言葉を綴る。しっとりと沁み込んでくる言葉の温度。
「いつの間にか、夢中になれるもんになってた」
幾度も聞いたことなのに、初めて聞かされている気分になる。
真っ直ぐに見つめてくる瞳を、見つめ返した。
「俺に跳ぶことを教えてくれたあの選手に、――華保に……すげー感謝してんだ」



