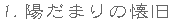
-16-
心地いい音程で綴られる言葉達に、包まれる。優しい空気が纏う。礼を言いたいのは、華保の方だった。
脚が駄目になったと判った時、二度と這い上がれない闇に囚われた。
ハイジャンさえしていなければ、知らなければ、こんな脚になることはなかった。だからといって、跳んでいた頃の自分を否定はしない。あの頃、あれが総てで大切だったことを、後悔はしていない。
それを、判ってくれていた人がいた。華保を、認めてくれていた人がいた。
無駄ではなかった。大切にしていてもいいのだと、言われている気がした。
「華を保つ」
そらんじるように、唐突に良尚は言った。静かな口調は維持されたまま。
ただ、放たれた意味が読み取れず、首を傾げた。
穏やかに良尚は笑み、続けた。少し照れ臭そうに。
「華保の名前、そう書くだろ?ぴったりだな、って思ってさ。――ハイジャンには華があった。そしてそれは、少しも損じることなく、思い描くことができるんだ」
言い切って、くしゃりと顔を歪ませる。ひどく恥ずかしかしそうだった。
「あたし…、自分の名前をそんな風に考えたことなかった」
急に愛しいものに思える。
「少なくとも俺は、そう思ってきたんだ」
柔和に綻ぶ。心があたたかく満たされていく。
青空が好きだった。
――いつか、取り戻せるだろうか。
幼き頃と同じ気持ちを。空を独り占めできたあの瞬間の気持ちを。
青空の下でも脚が痛くなることがないように、なれるだろうか。惨めなままでいたくない。強く、なりたい。
吹っ切って、前に進んでいきたい。
「ありがと、良尚」
がんばるから、と強く誓う。現実から目を逸らすのは、あれを最後にしたい。
「なんかあれば、言ってくれよな?」
正面きって言われると、何となく照れ臭い。
「心強いね」思わず揶揄を帯びた口調になってしまった。
「そう思ってもらえんなら、光栄だな。そこで一つ、提案なんだけどな」
それまでの空気をがらりと変化させる。良尚ほど早々に切り替えがつけられず、戸惑う。
「提案?」
「俺の従兄弟が陸部の顧問なんだけどさ」
話の流れが全く掴めない。一体何の話なのだ、と目を合わせるも、良尚は飄々としたもので。
「華保の学校の、柏倉って先生知ってる?」
「え、うん。直接教わったことはないけど」
新卒で採用された数学教師で一年生の副担任をしている筈だ、と記憶を手繰り寄せる。
人当たりの良さに加えて、整った容姿のおかげで人気があると、噂で聞いたことがあった。何度か見かけた時には、必ず数人の生徒が傍にいた気がする。
「柏倉伊織が従兄弟でさ、陸上競技知識の知の字も無い人間で」
押し切られたのだな、と容易に想像がつく。
まさか、と訝った矢先、予感的中。
「華保にコーチ、頼めないかと思って」
清々しいほどの軽い口調につられそうになって、慌てて意識を引き締めた。
「無理に決まってるじゃない」
現役高校生がコーチだなんて聞いたことがない。しかも、陸上を離れて年数が経っている上に、脚はこんな状態なのだ。
「決まってないだろ」
「本気?」
「めちゃくちゃ本気」
正気?とはさすがに問えない。
当然だろう、といわんばかりの自信満々さに、自分が間違っているのかと疑いたくもなった。
断る、というか、説得する言を捜している隙に、良尚は続けた。
「引き受けちゃったし」
「へ?」
「嘘」良尚は反応を楽しんでいるようでもある。「回答は保留中だけど、でもたぶん大丈夫、とは言っといた」
「大丈夫、という日本語の意味が判らなくなった」
「華保なら出来る」
その自信の根拠はどこだ、と半ば恨めしげに良尚を見た。
人に教えたことすらないというのに、コーチなんて無理。としか結論の出しようがない。
大体、お手本を示すことも出来ない者を、コーチだと認める人間がいるとは思えなかった。自分だったらまず認めない。
「根拠がないよ」
「俺の勘、って言ったら怒るか?」
「呆れるかもね」
「つれないお言葉で」ふざけておいて、ついと真剣な空気を纏う。「大変なのは判ってんだ。学校とセンター通いだけでもすげーなって思ってるよ。けど、」
ほんの短い沈黙に、身構えた。背筋が伸びる思いだった。
「――完全に克服しないか?」
凛と、力強い声音だった。
華保の芯に触れる言の葉。身体の奥に沈んでいた何かが眠りから醒める。



