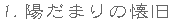
-17-
「もがいて、自力でどうにかできることにも、限界はある。周囲に頼るのは決して悪いことじゃない。真正面から向き合うことで、路は啓けるかもしれない」一人で、強くなることだけを考えてきた。
人に頼らずにいくことが、そうなれるのだと信じてきた。
総てを見透かされているようで居心地が悪く、けれど、嫌な気分ではなかった。
頑なでいる必要は、無かったのだろうか。
「大丈夫。ちゃんと最後まで付き合うから。なんか起こっても、二人で解決していこう」
従兄弟は変な奴じゃないし、と付け加え、笑う。
「まぁ、急な話だし。考えといて?」
太陽みたいな明るさで笑顔を向けられるだけで、やれそうな気がしてくるから、我ながらゲンキンだとは思う。
同時に、自分はこの人が好きなんだと、強く自覚していた。
「雨、緩んできた。これくらいなら傘でいけるな」
華保にとっては密度の濃い話ばかりが続き、深く考える必要のない天気の話題にどこかほっとする。
「ほんとだ。けど、時間も遅くなってきてるし、少し待ってくれたら母さんも帰る時間になるよ?」
「気持ちだけ有り難く受け取った。俺は本当に平気だって」
「判った。じゃー傘貸すね」
「助かる。それとさ、華保」
誰のものかも判らない置き傘はセンターに何本もあった。それを取りにいってからその次は、と脳内で今後の行動を組み立てる。
だから、視線を感じて良尚の方を向いた時、その真摯な眼差しに鼓動が大きく鳴った。
不意打ちは心臓に悪い。
音が漏れてしまわないかと、有り得ない心配をしてしまった。
「なに?」
「俺さ、舞阪華保が好きなんだ」
さらりと言われ、ぽかんと見つめ返した。
繰り出された言葉に理解処理能力が追いついていかない。遅れて処理が完了しても、思ってもみなかった現実に、え、と漏らすだけだった。
咄嗟に、聞き間違えたのだと決め付けたものの、良尚は同じことを繰り返した。
「返事、急がないから。考えてくんないか?」
「幻聴じゃないんだ」
茫然として自身の頬をつねる。痛い。
「幻聴じゃないよ」
良尚は華保の間抜けな所作に小さく笑い、ほう、と息を吐き出した。
いつでも一枚上手なわけじゃないんだ。
ポーカーフェイスに見えていたけれど、良尚も緊張していたのだと判明して、嬉しくなる。
浮き立ちついでに言っちゃうけど、と前置きする良尚の頬は、少し赤みがさしていた。
「華保が今まで見てきた世界をさ……これから見る筈だった世界を、俺が代わりに見てくから。傍にいて見守っててほしい」
一気に吐き出し、ぱっと目を逸らした。耳まで赤い。
こんなにも嬉しくて幸せなことはないと思う。
華保が無言であることを戸惑っていると勘違いしたのか――実際は実直に表現できる言葉を捜していたのだけれど――矢継ぎ早に後を紡いだ。
「…って、ごめん。なんか俺、余裕ないな。さっきまでの話だけでも華保には許容オーバーだろうにさ」
返事はあとでもいいと言って、それを貫こうとする空気を醸し出されて、華保は返事を飲み込んでしまった。
ついでに、若干落ち着きを失くしている良尚につられ、慌てて放った言葉は揶揄を孕んでしまって。
「良尚でも緊張するんだ?」
「俺をなんだと思ってるんだよ」
知らず肩に力がこもっていたらしい。良尚もそうだったと知ると、途端に緩んだ。
正面玄関に着く頃には、嵐然とした天候が嘘のように落ち着いていた。音も無く降る雨に風は混ざらず、傘があれば充分に歩けそうだった。
並んで歩くぎこちなさが、くすぐったい。
お互いに平然を装っていたけれど、どうしてもぎこちなさは拭えなかった。
三和土は玄関ホールより一段低くなっているのに、そこで靴を履き替えた良尚の身長は華保よりも高かった。
中学の時は小柄だった華保も、高校に上がって女子の平均ほどには伸びていたけれど、おそらく良尚は男子の平均よりも長身なのだろう。
「傘借りてくな」
「うん。気をつけて」
「じゃあ、な」
「うん」
意識するなって方が無理、と思っていたのは華保だけではない。
一瞬の逡巡ののち、緊張して若干強張り気味の表情を引き締めたまま、言った。
「返事、急がないって言ったけど…。いや、急がないんだけど、ちゃんと考えてほしい。冷静な時にでも」
冷静な時なんてこれに関しては訪れないと思うよ、とは内心で呟いておいて、表面では快諾を示しておいた。
じゃあ、と言って踵を返した良尚が、くんっと後ろに引っ張られた動きをとった。なにが、と問おうとして、自分の指が良尚の制服を掴んでいたことに驚く。
無意識の行動は末恐ろしい。
自身の行動に驚いているのだから、巧い言い訳なんか浮ぶわけがない。振り払うほどの勢いで手を離すも、やらかしたことは消えない。
「ごっ、ごめんっ!なにやってんだろ、あたしっ」
「びっくりしたっての」良尚は振り返らない。
意味不明な行動に怒っているのかと見上げたら、真っ赤に染まる耳が見えた。
華保の顔面も熱が上昇しっぱなしだ。
「き、気をつけてっ…ね」
「さっきも聞いたって」ふ、と笑音がするも、やはり良尚は振り返らなかった。
頭の中が混乱する。混乱するままに「じゃあね!バイバイッ」と言って、走って逃げた。
振り返られたらもう、どうしていいか判らない。逃げるが勝ち。



